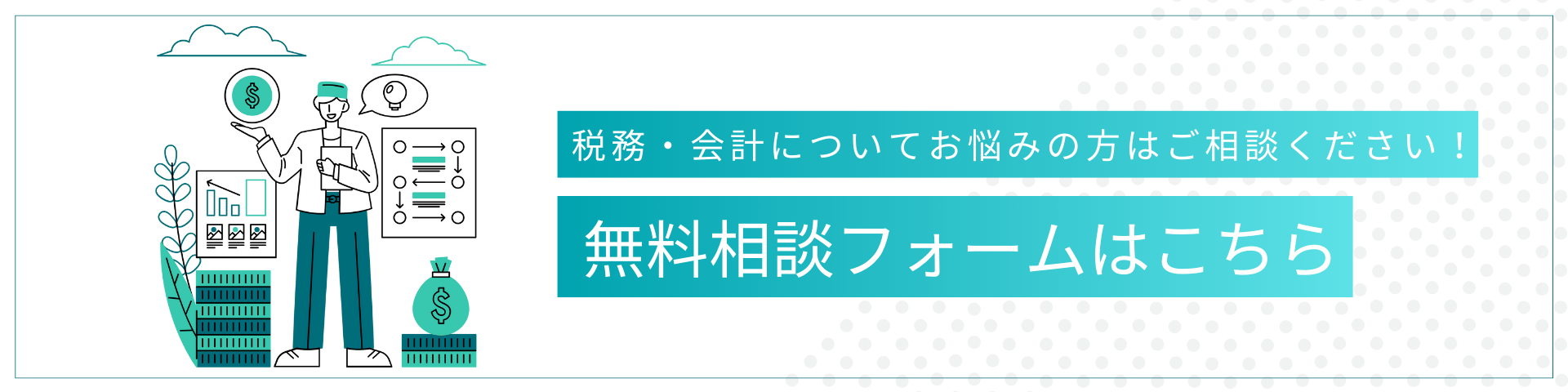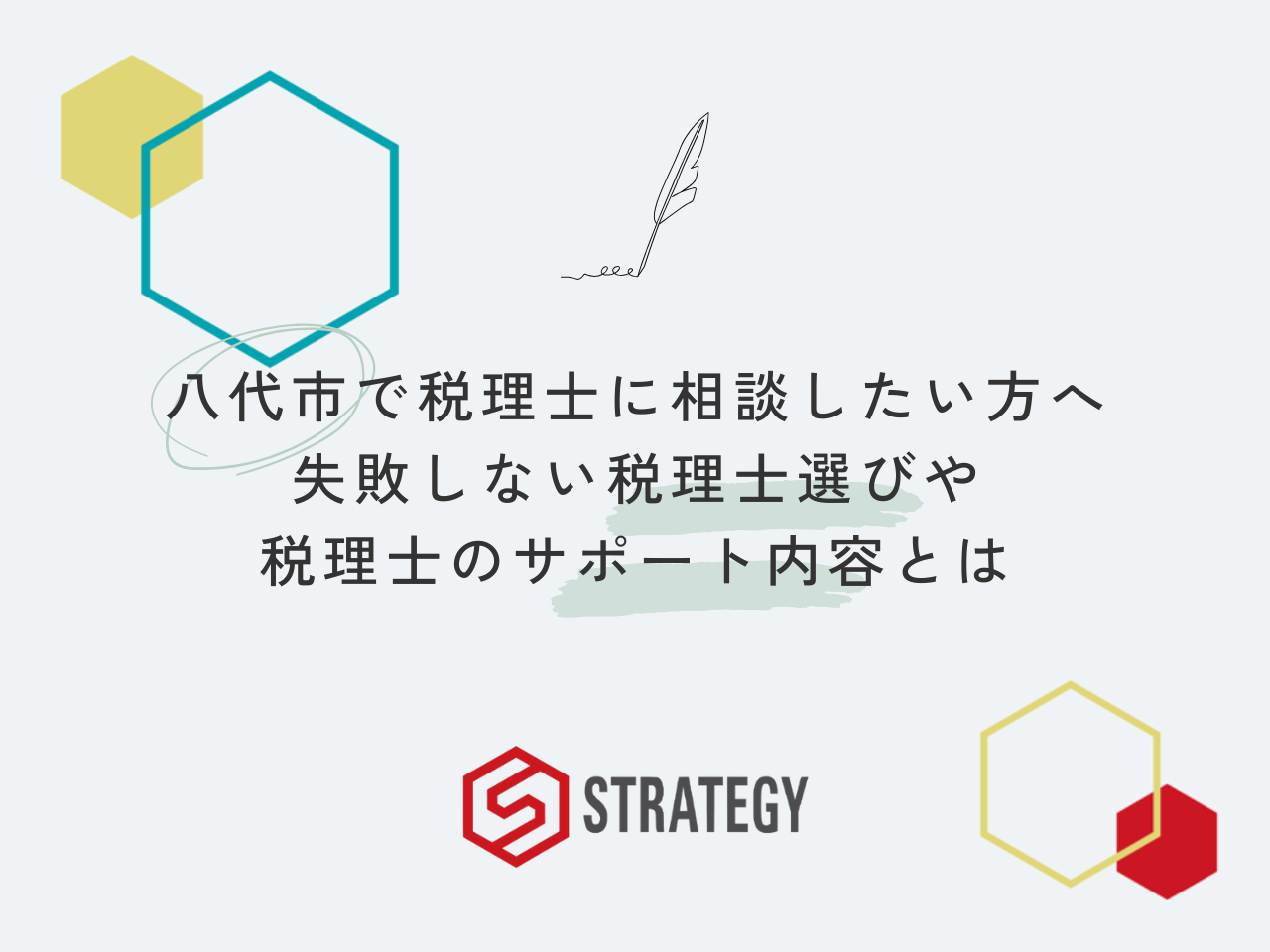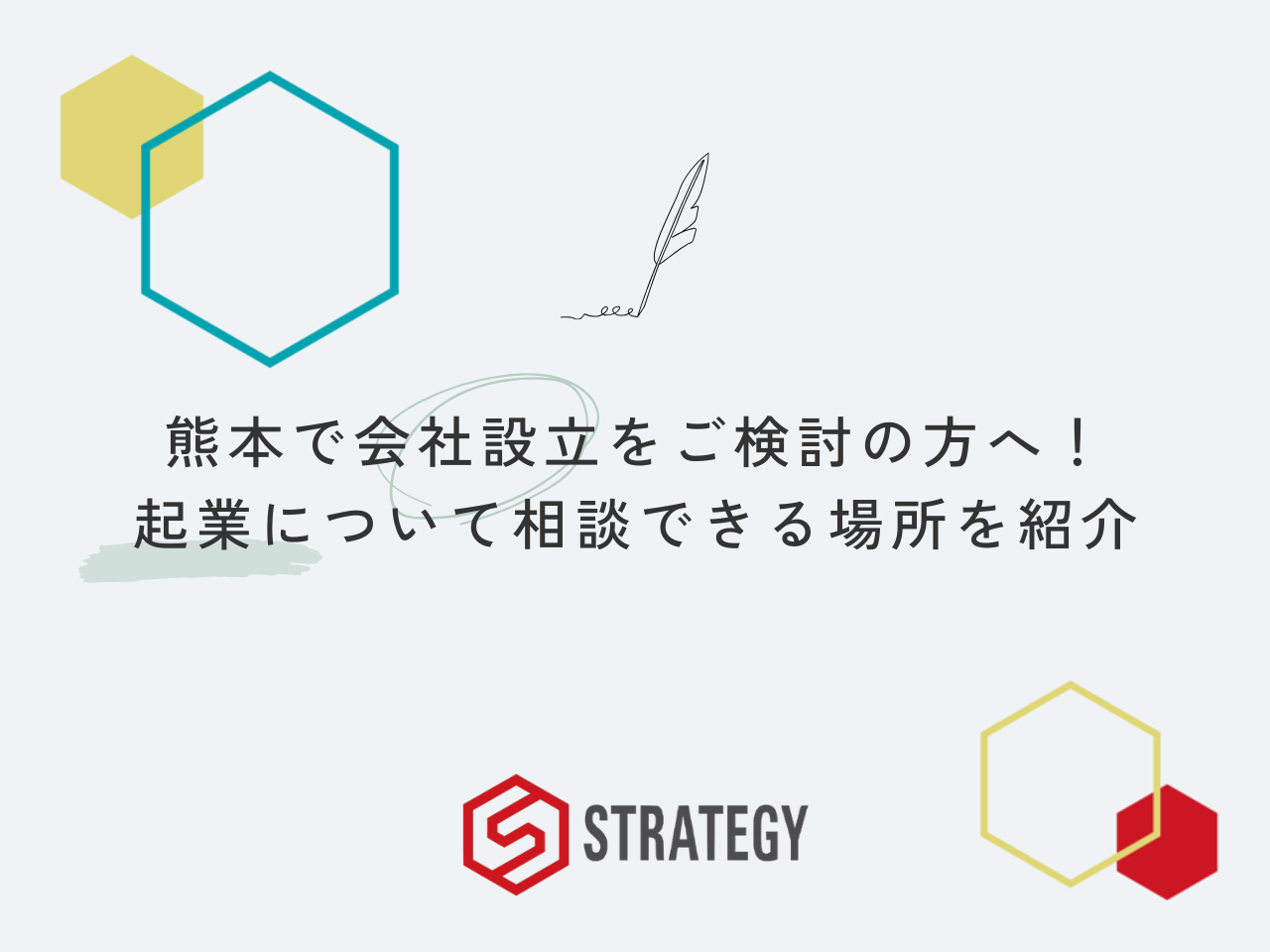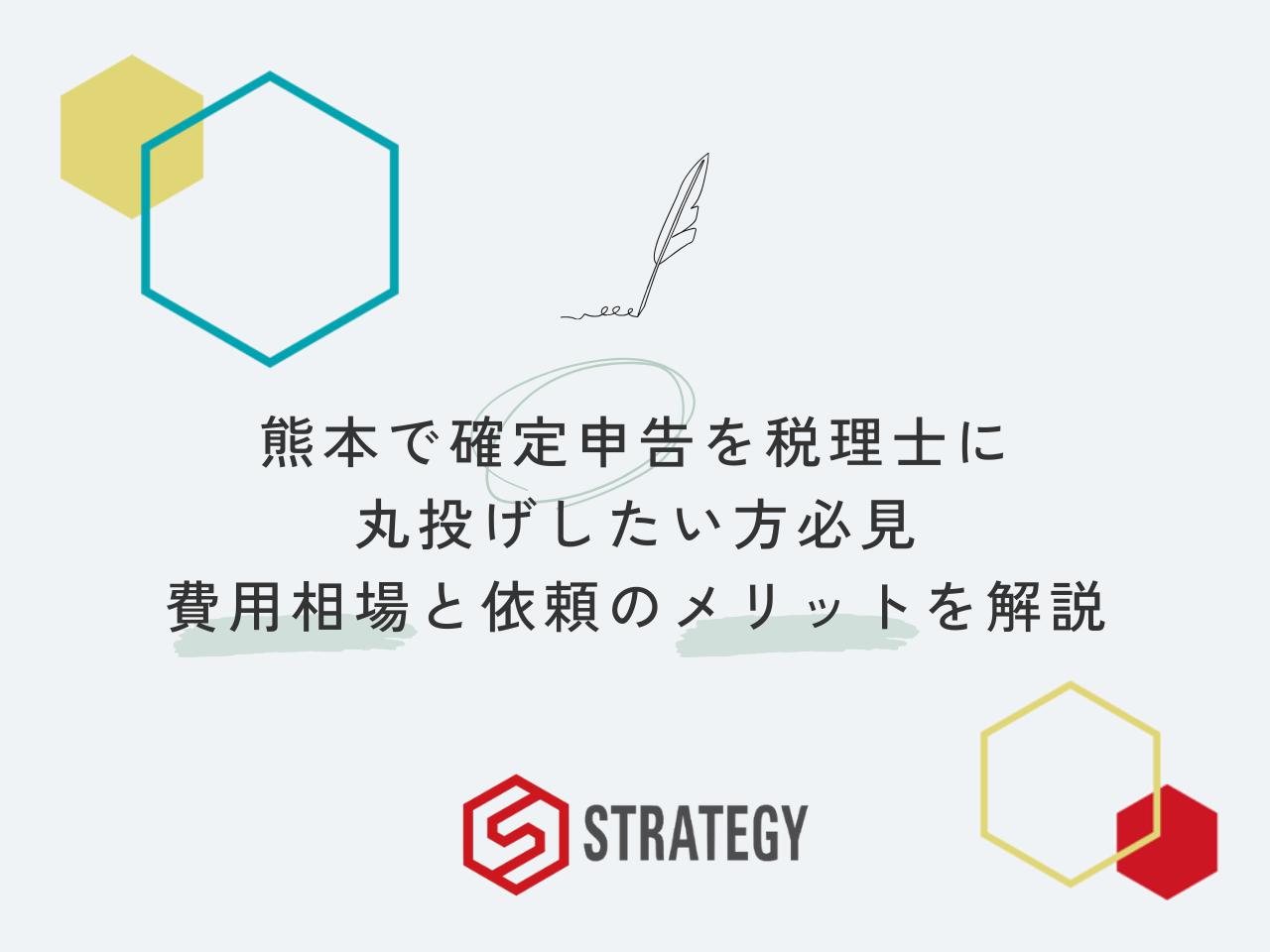経理担当者が突然退職…どうする?今すぐ取るべき対処法を解説!
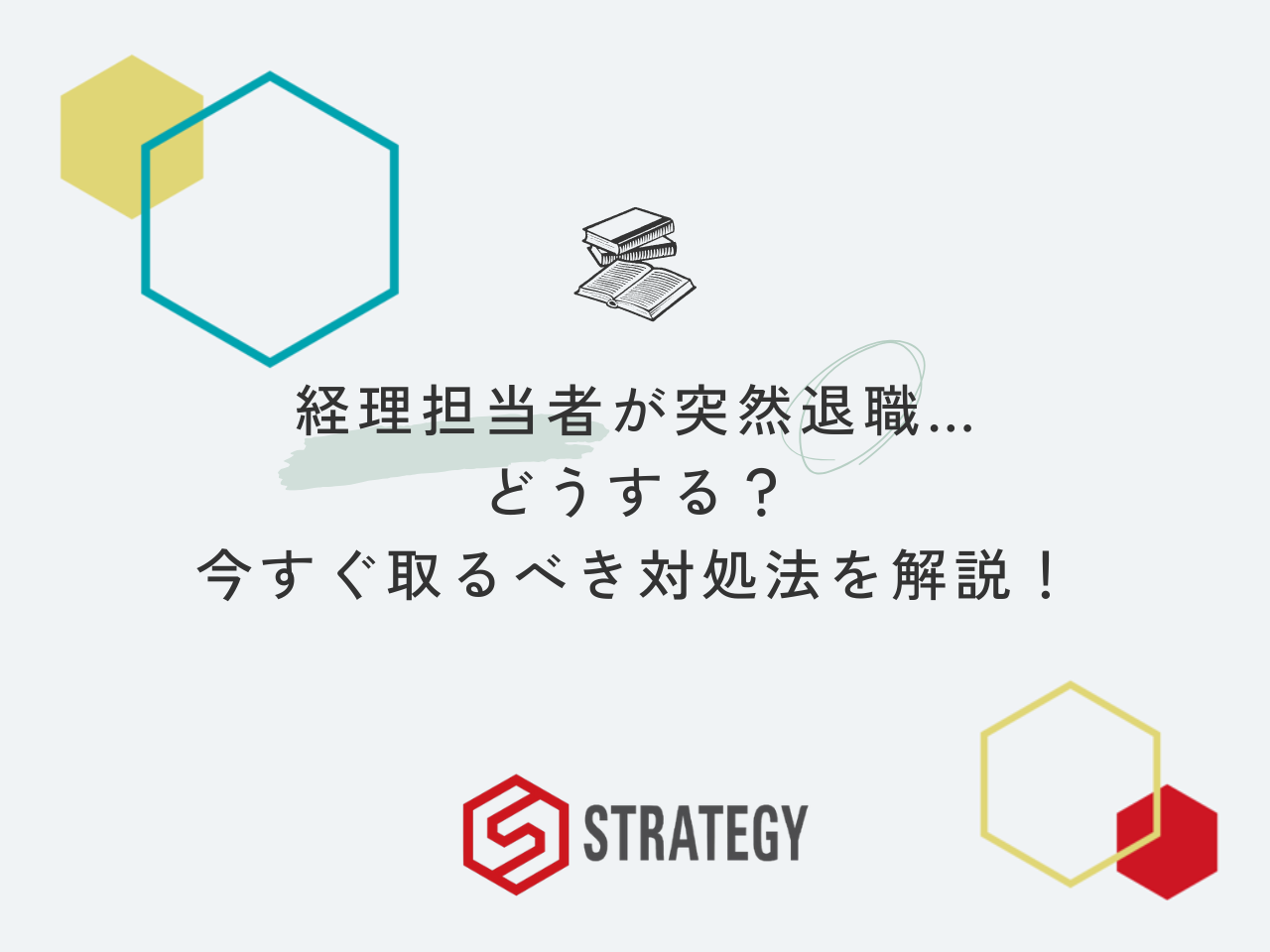
「うちの経理が突然辞めることになって…どうしたらいいのか分からないんです…」
そんなご相談を受けること、実は少なくありません。
中小企業や個人事業主の現場では、経理担当者が1人というケースも多く、その人が退職してしまうと、請求書の処理や給与計算、さらには決算業務までがストップしてしまう可能性があります。
しかも、「後任がすぐに見つからない」「経理内容がブラックボックス化している」など、焦りや不安を抱える経営者の方も多いのではないでしょうか。
でも大丈夫です!
経理担当者の退職は確かに大きなインパクトですが、冷静に状況を整理し、必要な対応を順序立てて行えば、業務を止めずに乗り越えることが可能です。
さらに、このタイミングで経理体制そのものを見直すチャンスにもなります。
本記事では、経理が退職したときに会社がまず取るべき対処法から、社内対応の限界と外部委託の選択肢、さらには経理業務の再構築までを、税理士の視点でやさしく解説していきます。
「何から手を付けたらいいか分からない…」という今の状態から、「とりあえず、これをやれば大丈夫!」という安心感を生むような内容になるようお伝えします。
ぜひ最後までご覧いただき、今後の対応の参考にしてください🍀
目次
1.経理担当者が退職したとき、会社がまずやるべき3つのこと
1.1.①経理業務の棚卸とマニュアルの確認
1.2.②社内での一時対応体制の構築
1.3.③社外の専門家・外注先の検討
2.そもそも経理がいなくなると何が困る?
2.1.経理業務が滞ることで起きる具体的なリスク
2.2.中小企業だからこそダメージが大きい理由とは
3.社内で引き継ぐ?外部に依頼する?それぞれのメリット・デメリット
3.1.社内で代替するケースのメリット・デメリット
3.2.税理士・専門業者に外注するケースのメリット・デメリット
4.経理代行・税理士に依頼するとどこまで対応してもらえる?
3.1.日々の記帳から決算・申告まで幅広くサポート
3.2.経理体制の再構築までサポートしてくれるところも
4.経理が退職してしまった後のよくある質問
4.1.Q1:急に経理が退職して、過去の資料がぐちゃぐちゃ…。どうすればいい?
4.2.Q2:経理未経験の社員に任せるのはアリ?
4.3.Q3:どのタイミングで外注すればいい?
5.まとめ
経理担当者が退職したとき、会社がまずやるべき3つのこと
経理担当者が退職したとき、まず何よりも大切なのは、パニックにならずに、やるべきことを一つずつ整理することです。
ここでは、会社が最初に取り組むべき3つの対処法をご紹介します。
①経理業務の棚卸とマニュアルの確認
まず取り組むべきは、経理担当者がどの業務を担っていたのかを可視化することです。
- 毎日の記帳・仕訳入力
- 請求書の発行や支払い管理
- 給与計算
- 年末調整・決算資料の作成
- 税務署への提出物の準備 など
もし、マニュアルやチェックリストが残っていれば、それをもとに業務の全体像を把握しましょう。
しかし、経理業務が属人化していた場合、「何をやっていたのか分からない…」ということも少なくありません。
その場合でも、過去の帳簿や仕訳記録、会計ソフトの履歴などをもとに、どの業務が止まっているのか・いつまでに対応が必要かを洗い出すことが第一歩となります。
②社内での一時対応体制の構築
次に行いたいのが、社内での一時的な対応体制の構築です。
すぐに後任が決まらないケースも多いため、まずは経理業務の中でも「期限がある重要な業務(支払い、給与計算、税務申告など)」を優先して、代替できる人材に割り振りましょう。
ポイントは、完璧を求めすぎないこと。
あくまでも「急場をしのぐ仮の対応」として、できる範囲で体制を作ることが重要です。
また、社内での対応に限界を感じたときは、早めに外部への相談も視野に入れると安心です。
③社外の専門家・外注先の検討
経理業務は専門性が高く、ミスが許されにくい分野です。
社内対応だけではリスクが大きいと判断した場合には、税理士や経理代行サービスなどの外部の専門家への相談・依頼を検討しましょう。
例えば税理士法人ストラテジーでは、
- 経理の現状整理
- 急な退職時のスポット対応
- 経理業務の継続的な代行・効率化支援
などの柔軟な対応が可能です。
「誰かに頼るのはまだ早いかな…」と思われる方も、まずは無料相談で話を聞くだけでも、状況を客観的に整理できます。
👇 詳しくはこちらから無料相談をご利用いただけます!👇
そもそも経理がいなくなると何が困る?
経理担当者が退職してしまうと、「とりあえず数日は大丈夫かな…」と楽観視してしまうこともあるかもしれません。
しかし、経理という業務は水面下で日々の会社の運営を支える土台となっており、担当者がいなくなることでさまざまなリスクが一気に目に見えてきます。
次に、経理業務が止まったときに起こりうる問題と、特に中小企業における影響について見ていきましょう。
経理業務が滞ることで起きる具体的なリスク
経理が不在になることで生じる問題は、単に「帳簿が付けられない」だけではありません。
以下のような経営全体に影響を与えるトラブルが発生する可能性があります。
- 取引先への請求書の発行が遅れ、入金が遅延する
- 支払い処理が滞り、信用問題に発展する
- 給与計算や社会保険の手続きが間に合わない
- 会計ソフトやデータの管理方法が不明確で、状況把握ができない
- 決算や税務申告に間に合わず、延滞税・加算税が発生する
これらはすべて、「会社のお金の流れ」が見えなくなることによって起きるものです。
日々の仕訳や月次の集計が止まってしまうと、経営判断に必要な数字がつかめなくなり、資金繰りにも悪影響が出てしまいます。
中小企業だからこそダメージが大きい理由とは
特に注意すべきなのが、中小企業や小規模事業者ほど、経理がいなくなるダメージが大きいという点です。
その理由は、
- 経理を一人に任せきりにしているケースが多く、属人化しやすい
- 経営者自身が現場を兼務しており、すぐに経理まで手が回らない
- 突然のトラブルに備えるバックアップ体制が整っていない
といった事情があるからです。
たとえば、ある日突然「支払いの期日が過ぎていた」「税金の申告を忘れていた」といった事態が起きたとき、誰も対応できない…ということになれば、取引停止や罰金など、事業の継続自体に関わる深刻な問題に発展しかねません。
「経理の仕事って、何となく地味に見えるけど、実は会社の命綱だったんだな…」と気づくのは、辞められた“後”ということも少なくないのです。
社内で引き継ぐ?外部に依頼する?それぞれのメリット・デメリット

経理担当者が退職した後、経理業務をどのように引き継ぐかは会社にとって大きな決断です。
多くの企業が悩むのが、「社内でなんとか対応するべきか、それとも外部に依頼するべきか」という点です。
ここでは、それぞれの選択肢について、メリット・デメリットを比較しながら検討してみましょう。
社内で代替するケースのメリット・デメリット
まずは、社内で対応する場合です。
既存の社員が一時的に経理業務を引き継ぐことで、新たな外注費用はかかりませんし、社内の業務フローや取引先についても把握しているため、スムーズに進めやすいというメリットがあります。
しかし一方で、経理の知識や経験がないまま業務を任されると、ミスや漏れが発生するリスクが高くなります。
また、他の業務と兼任になることで、社員に大きな負担がかかり、ミスだけでなくモチベーションの低下や業務の遅れにもつながりかねません。
さらに、経理を“なんとなく”対応できる人に任せてしまうと、また同じように属人化が進み、次にその人が退職したときも同じ問題が起きるという悪循環にもなりやすいのです。
✅ メリット
- 社内業務の流れを熟知しているため、スムーズに対応できる可能性がある
- 新たな費用が発生しない(人件費の追加がない)
- 経理業務を内製化し続けられる安心感がある
❌ デメリット
- 他の業務との兼任で、社員に負担が集中しやすい
- 経理の知識や経験がないと、ミスやトラブルの原因になりやすい
- 結局また属人化してしまい、同じ問題が繰り返されるリスクがある
一時的に乗り切るためには社内で対応するのも有効ですが、長期的に見て経理体制を安定させるには限界があることも事実です。
税理士・専門業者に外注するケースのメリット・デメリット
もう一つの選択肢が、税理士事務所や経理代行業者などの外部の専門家に依頼する方法です。
この方法の一番のメリットは、やはり正確でスピーディーな対応が期待できること。
経理のプロに任せることで、日々の記帳業務から給与計算、さらには決算や税務申告に至るまで、安心して任せることができます。
最新の税法や会計ソフトの知識を持ったプロだからこそ、ミスを防ぎ、業務の効率化も図れるのが魅力です。
また、経理体制そのものを見直すきっかけにもなるため、これを機に「よりよい経理の仕組み」を作る企業も少なくありません。
もちろん、費用面では一定のコストが発生しますし、引き継ぎ時には情報整理などの準備も必要になります。
ただ、その手間を上回る安心感や、経営者自身が本業に集中できるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
✅ メリット
- 専門知識をもったプロが正確・効率的に対応してくれる
- 税務申告や法改正にも対応してもらえるため安心感が高い
- 社長や社員が本来の業務に専念できる
- 経理の効率化や仕組みづくりまで提案してもらえるケースもある
❌ デメリット
- 一定の外注コストがかかる
- 最初の引き継ぎには情報整理の手間が発生する
- 業者選びを間違えると、対応や質に不満が出ることも
ただし、信頼できる専門家に依頼できれば、経理体制を根本から見直し、将来的な業務の安定やコスト削減につながることも多いのです。
税理士法人ストラテジーでは、
- 突発的な経理担当者の退職への「緊急対応」から
- 継続的な経理代行、
- 経理体制の見直しや効率化支援
まで、幅広くサポートしています。
「とにかく今どうすればいいのか分からない…」という段階でも大丈夫。
まずは無料相談で、現在の状況を共有することから始めてみてくださいね。
関連記事:経理代行とは?頼める業務の内容や税理士に頼むメリットとは?
経理代行・税理士に依頼するとどこまで対応してもらえる?
「外部に頼むっていっても、実際にどこまでやってもらえるの?」
そう感じる方もきっと多いと思います。
経理担当者が突然いなくなったあと、「何を、どこまで、誰にお願いしていいのかわからない…」という状態になってしまうのは当然のこと。
でもご安心ください。経理代行や税理士への依頼は、全部じゃなくてもOKなんです。
必要なところだけを任せたり、逆に「この際だからまるっとお願いしたい」というご相談にも対応できます。
次に、実際に依頼できる内容について、わかりやすくご紹介します。
日々の記帳から決算・申告まで幅広くサポート
経理代行や税理士が対応できる業務として、たとえば以下のようなことがお願いできます。
- 領収書や通帳データをもとにした日々の記帳代行
- 請求書の発行や支払い管理のサポート
- 給与計算や年末調整の処理
- 決算書類の作成・法人税等の申告代行
- 税務署や役所への提出物の対応
こういった業務は「いつまでに・どこまでやるか」が明確なので、外部に任せた方が確実で安心というケースが多いです。
特に「決算や申告が近づいている…」という場合は、早めに相談することでトラブルを未然に防げますよ。
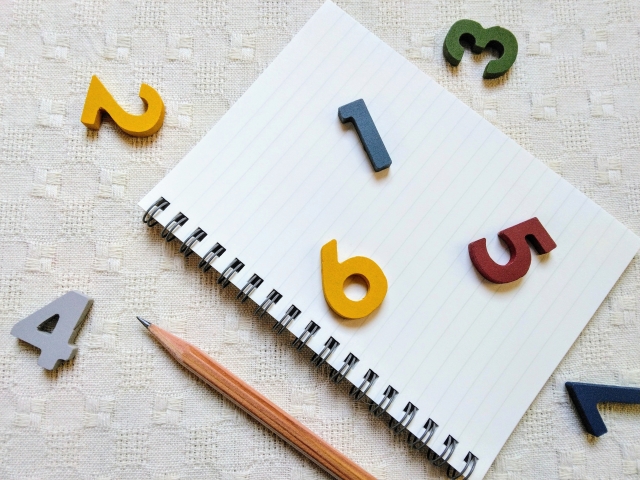
経理体制の再構築までサポートしてくれるところも
実は、経理代行や税理士は「ただ作業をこなすだけ」ではありません。
会社の状況に応じて、より効率的な経理体制の見直しやアドバイスをしてくれるところも多いんです。
たとえば、「毎月の数字をもっと早く見たい」「経理が属人化しない体制をつくりたい」といった悩みにも、
- クラウド会計ソフトの導入支援
- フローの簡素化・マニュアル化の提案
- 社内担当者との連携体制づくり
など、経理を強くする仕組みづくりという視点で伴走してくれます。
実際、税理士法人ストラテジーでも、「退職をきっかけに、むしろ経理がラクになった!」とおっしゃるお客様もいらっしゃいます。
一時的なサポートにとどまらず、「これからの経理」を一緒に考えてくれる存在として頼れるのが、専門家に依頼する大きな魅力です。
関連記事:個人事業主こそ経理代行を活用すべき理由とは?メリット・デメリットや選び方まで徹底解説!
経理が退職してしまった後のよくある質問
経理の方が突然辞めてしまったあとの状況は、本当に人それぞれ。
「うちだけこんなに大変なんじゃないか…」「こんな状態でも相談していいのかな…」と不安に感じている方も多いかもしれません。
でも大丈夫です!
ここでは、実際に寄せられることの多いよくある質問を取り上げてみました。
あなたの悩みに近い内容があれば、ぜひ参考にしてみてくださいね。
Q1:急に経理が退職して、過去の資料がぐちゃぐちゃ…。どうすればいい?
A1:まずは焦らず、現状を整理することから始めましょう。
「領収書が散らばっている」「会計ソフトの使い方も分からない」など、経理担当者がいないことで「何がどうなっているの?」となってしまうことは珍しくありません。
そんなときは、資料や帳簿を時系列で並べてみるだけでも一歩前進です。
そこから「何が足りないか」「何を急いでやる必要があるか」が見えてきます。
また、税理士などの専門家に相談すれば、混乱した状態からの整理や修正にも対応してもらえるので、心配しすぎなくて大丈夫ですよ。
Q2:経理未経験の社員に任せるのはアリ?
A2:一時的な対応は可能ですが、無理は禁物です。
人手が足りない状況だと、つい「とりあえずあの人にお願いしよう」と経理未経験の社員に任せたくなってしまいますよね。
ただ、経理業務にはミスが許されない部分も多く、知識がない状態での対応はかえってリスクが大きくなることも。
もし任せる場合は、
- ルールを明確に決めておく
- 外部のサポートを受けながら進める
- 限られた範囲(例:領収書の整理やデータ入力)に絞る
といった形で、無理のない範囲でフォロー体制を整えることが大切です。
Q3:どのタイミングで外注すればいい?
A3:迷っている段階で、一度相談してみるのがおすすめです。
「社内で対応できそうだけど不安がある…」「今すぐ外注するほどではない気がする…」というときほど、早めに専門家に相談しておくことが安心につながります。
特に、
- 近々決算がある
- 税務署から書類が届いた
- 資金繰りが見えなくなってきた
といった状況では、時間との勝負になることも。
税理士や経理代行のプロに相談することで、会社に合った対応の優先順位や進め方を整理してもらえるので、気持ちもグッとラクになりますよ。
まとめ
経理担当者の突然の退職――
それは、どの会社にも起こりうる“想定外”の出来事です。
でも、この記事を通じてお伝えしてきたように、
「何を優先すべきか」を整理して一つずつ対処していけば、焦らず乗り越えることは十分に可能です。
- まずは経理業務の棚卸から始める
- 一時的に社内で対応できる部分を明確にする
- 必要に応じて、信頼できる専門家にサポートを依頼する
この3ステップを意識するだけで、経理の混乱は落ち着きを取り戻しますし、
むしろ「経理体制を見直すチャンス」になることも少なくありません。
…とはいえ、「どこから手をつければいいのか分からない!」という方がほとんどです。
そんなときは、どうか一人で抱え込まずに、まずは私たちにご相談ください!
税理士法人ストラテジーでは、
経理の引き継ぎや代行はもちろん、経理業務全体の整理・再設計までトータルでサポートしています。
「まだ依頼するかは決めていないけれど、話だけ聞いてみたい」
そんなお気持ちでも大丈夫です。
無料相談で、あなたの会社の現状を丁寧にお伺いし、本当に必要なサポートだけをご提案いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の経理体制が、これからもっとスムーズに、そして安心できるものになりますように🍀
\無料でご相談いただけますのでお気軽にご連絡ください☺/