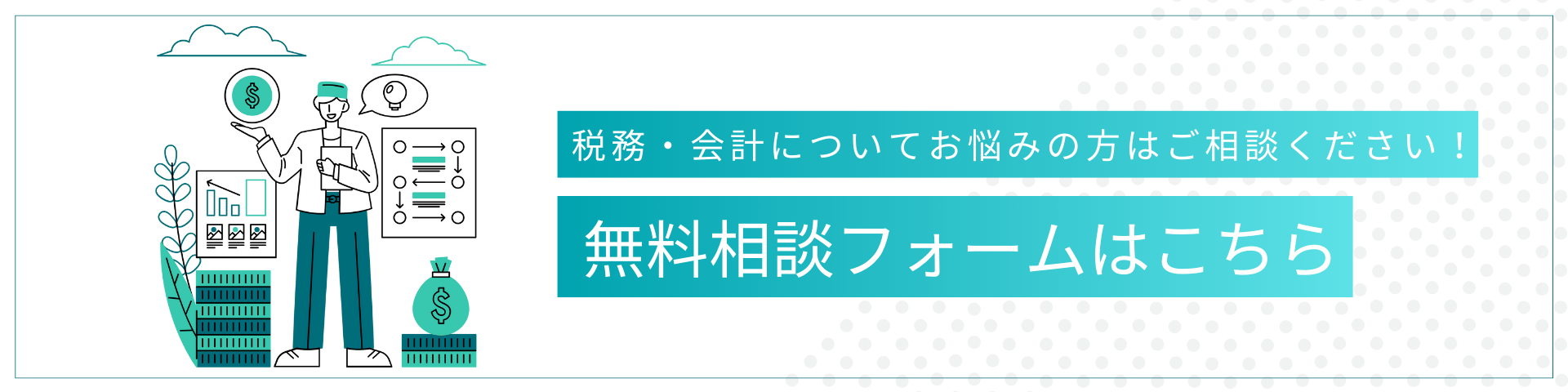建設業に特有の会計処理とは?熊本の税理士が教える実務の注意点!

建設業の経営者や経理担当の方からよく聞かれるのが、
「建設業の会計はほかの業種と何が違うの?」
「決算や税務申告のときに、どこに注意すればいいの?」
といった疑問です。
実は、建設業には工事進行基準や完成基準といった特有の会計ルールがあります。
そしてさらに工事ごとに原価を管理しなければならないなど、一般の業種とは大きく異なる会計・税務のポイントがあります。
これらを正しく処理できていないと、思わぬ税務調査リスクにつながったり、融資や経営事項審査(経審)の場面で不利になってしまうことも少なくありません。
特に熊本の建設業者の方からは、
- 「工事代金の入金と支払いのタイミングが合わず、資金繰りが大変」
- 「経審で点数を上げたいけれど、決算書の作り方が分からない」
- 「税理士に頼んでいるのに、建設業特有の処理に詳しくなくて不安」
といった声が多く聞かれます。
本記事では、熊本で建設業を営む経営者の方に向けて、建設業に特有の会計・税務処理のポイントを解説します。
さらに、実務で注意すべき点や税理士に依頼するメリット、成功事例についても紹介しますので、ぜひご参考になさってください。
目次
1.建設業の税務・会計は一般業種とどこが違う?
1.1.工事進行基準と完成基準の違い
1.2.材料費・外注費が多い業種特性
1.3.売上入金のタイムラグと資金繰りの難しさ
2.建設業における会計処理の実務ポイント
2.1.工事ごとの原価管理の重要性
2.2.完成工事未収入金・未成工事支出金の扱い
2.3.消費税や源泉所得税で注意すべき点
3.建設業の決算や税務申告で気をつけたいこと
3.1.工事進行基準の適用
3.2.工事原価の正確な把握
3.3.決算調整仕訳の注意
3.4.消費税の課税取引
4.建設業でよくある税務調査の指摘ポイント
4.1.①工事完成基準・進行基準の誤り
4.2.②外注費と給与の区別
4.3.③領収書・請求書の不備
4.4.④交際費・福利厚生費の区別
4.5.⑤在庫や未成工事支出金の管理
5.建設業の節税対策とキャッシュフロー改善のヒント
5.1.節税対策のポイント
5.2.キャッシュフロー改善のヒント
6.建設業の会計・税務で専門家に相談すべきタイミング
6.1.①創業・会社設立のとき
6.2.②工事規模が大きくなったとき
6.3.③決算や税務申告を迎えるとき
6.4.④税務調査の通知が来たとき
6.5.⑤節税や資金繰りを考え始めたとき
7.まとめ
建設業の税務・会計は一般業種とどこが違う?

建設業は、製造業や小売業と比べても「会計や税務のルールが特殊」だと言われます。
その理由は、建設工事が長期間にわたり、契約ごとに金額も規模も大きく変わるためです。
一般的な事業と同じ感覚で処理してしまうと、税務上のトラブルや資金繰りの悪化を招く可能性があります。
ここでは、建設業ならではの大きな違いを整理してみましょう!
工事進行基準と完成基準の違い
建設業の会計処理でまず押さえておきたい点が、「工事進行基準」と「完成基準」です。
- 工事進行基準:工事の進捗度に応じて、毎期の売上や利益を計上する方法
- 完成基準:工事が完了した時点で、一括して売上や利益を計上する方法
大規模で長期にわたる工事は「工事進行基準」が求められることが多く、どの方法を選ぶかによって決算の数字が大きく変わることもあります。
もし誤った処理をすると、税務調査で指摘を受けたり、融資や経審に影響が出る可能性もあるため注意が必要です。
材料費・外注費が多い業種特性
建設業では、鉄骨や木材、コンクリートなどの 材料費 や、協力会社への 外注費 が大きな割合を占めます。
そのため「工事ごとにどれだけの原価がかかったのか」を把握しなければ、正確な利益を計算できません。
原価管理をおろそかにすると、赤字工事に気づかず経営を圧迫してしまうケースもあります。
売上入金のタイムラグと資金繰りの難しさ
建設業の大きな特徴は「先に支払いが発生し、入金は後から」という資金の流れです。
材料費や外注費は工事中に先払いするのに対し、売上代金の入金は工事完了後や数か月先になることも珍しくありません。
結果として、黒字決算なのに資金繰りが苦しい、という状況に陥りやすいのです。
このような特殊性を理解していないと、決算書だけでは「黒字なのに資金が不足」という矛盾に気づけず、経営判断を誤るリスクもあります。
建設業における会計処理の実務ポイント
建設業の会計は、工事ごとに発生する取引を細かく把握し、正確に処理することが求められます。
ここでミスがあると、決算や税務申告だけでなく、経営事項審査(経審)や融資審査にも影響を及ぼすため注意が必要です。
ここでは実務上、特に意識しておきたいポイントをお伝えします。
工事ごとの原価管理の重要性
建設業では「工事ごとの利益」を正しく把握することが非常に重要です。
工事原価には、材料費・労務費・外注費・経費などが含まれます。
例えば、材料の仕入を一括で処理してしまうと、どの工事にどれだけ費用がかかったのか分からなくなってしまいます。
結果として、赤字工事の発見が遅れる、原価を見直せない、といった経営上のリスクにつながります。
完成工事未収入金・未成工事支出金の扱い
建設業の決算書でよく出てくるのが「完成工事未収入金」と「未成工事支出金」です。
- 完成工事未収入金:工事は終わったけれど、まだ入金されていない売掛金
- 未成工事支出金:工事がまだ終わっていない段階で発生している費用
これらを正しく処理しないと、決算書の信頼性が低下し、経審や融資で不利になる可能性があります。特に金融機関は資金繰りを厳しくチェックするため、数字の整合性はとても重要です。
消費税や源泉所得税で注意すべき点
建設業では、下請業者や職人さんへの支払い時に、源泉所得税を天引きするケースがあります。
処理を誤ると税務署からの指摘を受けることもあるため、支払いのたびに正しく計算・納付することが欠かせません。
また、消費税についても工事請負契約ごとに発生時期が異なるため、「いつ消費税を計上するのか」「課税仕入と非課税をどう区分するのか」といった実務判断が必要になります。
\無料相談実施中です☺/
建設業の決算や税務申告で気をつけたいこと
建設業の決算や税務申告は、一般業種と比べて注意すべき点がいくつもあります。
特に「工事ごとの利益管理」が正しくできていないと、決算書に反映される数字も大きく変わってしまい、税額にも影響が出ることがあります。
ここでは、建設業ならではの決算・申告の注意点をまとめてご紹介します!
工事進行基準の適用
建設業の特徴的な会計処理の一つが「工事進行基準」です。
工事が長期にわたる場合、完成を待たずに工事の進捗度合いに応じて売上や利益を計上するルールがあります。
これを誤って「完成基準」で処理してしまうと、売上や利益が本来の期に反映されず、申告内容が大きくズレてしまいます。
特に公共工事を扱う会社では必須となるため、必ず確認しておきましょう。
工事原価の正確な把握
工事ごとに材料費や外注費、人件費を適切に振り分けていないと、原価が膨らんで赤字に見えてしまったり、逆に利益が過大に計上されたりします。
結果として、税額計算にも影響が出ます。
工事原価台帳をしっかりと整備し、工事単位で「どのくらい儲かったのか」が見えるようにしておくことが重要です。
決算調整仕訳の注意
決算では「未成工事支出金」「未成工事受入金」など建設業特有の勘定科目を整理する必要があります。
これを怠ると、貸借対照表が実態を表さなくなり、金融機関からの信用にも影響します。
これは融資を検討する会社にとっては、特に大きなチェックポイントです。
消費税の課税取引
建設業では「一括請負」や「部分請負」「下請け」など、契約形態が複雑なため、消費税の課税・非課税の判定に迷うことがあります。
特に課税事業者にとっては、適切な処理を怠ると追徴課税のリスクもありますので注意が必要です。
決算や申告は「年に一度だから」と後回しにしがちですが、建設業の場合は日々の仕訳や工事原価管理が積み重なって、決算の数字につながっていきます。
普段から正しい記帳を心がけることで、決算時に慌てることなくスムーズに進められますよ。
建設業でよくある税務調査の指摘ポイント

建設業は、現金取引の多さや工事が長期にわたる特徴から、税務調査で指摘を受けやすい業種のひとつです。調査官が特に注意して確認するのは「売上の計上漏れ」や「経費の適正性」といった部分です。ここでは、建設業に特有のよくある指摘ポイントを整理してみましょう。
①工事完成基準・進行基準の誤り
工事の収益認識は「完成基準」か「進行基準」で行いますが、これを誤って処理していると、売上の過不足が発生します。
特に進行基準を採用している場合、進捗率の算定方法や原価配賦が適切かどうかが厳しく確認されます。
②外注費と給与の区別
建設業では外注職人や一人親方に支払う報酬が多く発生しますが、「外注費」と「給与」の区分が不明確だと指摘されやすいです。
形式的には外注契約でも、実態が雇用に近ければ「給与」と判断され、源泉所得税や社会保険の未納を追及されるケースもあります。
③領収書・請求書の不備
材料費や雑費などで領収書の宛名が空欄だったり、簡易的なレシートしかなかったりすると、経費として認められない可能性があります。
特に現金取引では証憑の保存状況が厳しくチェックされます。
④交際費・福利厚生費の区別
得意先や協力業者との会食費を「福利厚生費」として処理してしまうと、税務調査で修正を求められることがあります。
交際費は上限や制限があるため、費目の振り分けを慎重に行う必要があります。
⑤在庫や未成工事支出金の管理
建設業では材料を大量に仕入れて工事ごとに使うため、「期末に在庫が残っていないか」「未成工事支出金の振替が適切か」が重点的に確認されます。
在庫管理や工事ごとの原価計算が甘いと、売上原価の過大計上とみなされてしまう可能性があります。
建設業の税務調査は、業種特有の処理の難しさから「思いがけない指摘」を受けやすいのが現実です。普段から帳簿や証憑の整理を徹底し、処理方法を誤らないようにしておくことが重要です。
\無料相談実施中です☺/
建設業の節税対策とキャッシュフロー改善のヒント
建設業を営んでいると、
「せっかく利益が出ても税金でかなり持っていかれてしまった…」
「工事代金の入金が遅くて、手元に資金が残らない」
と感じることはありませんか?
これは決してあなただけではなく、多くの建設業の方が抱えている共通のお悩みです。
そんな中で大切になるのが、「税金を払いすぎない工夫=節税」と「お金の流れをなめらかにする=キャッシュフロー改善」です。
ここでは、無理のない範囲で取り組めるヒントをご紹介しますね。
節税対策のポイント
まず節税の観点では、車両や重機の減価償却の見直しや、退職金制度・小規模企業共済などの活用が効果的です。
これらは将来に備える仕組みでありながら、今の税金を抑えることができるので一石二鳥。さらに、消耗品や経費の記録をこまめにつけておくことも重要です。
意外と小さな領収書の積み重ねが、節税につながるケースも多いんです。
- 必要な経費をきちんと計上する
建設業は資材費・外注費・人件費など経費の種類が多く、計上漏れが起こりやすいです。特に外注費は、契約書や領収書をきちんと整備しておかないと税務署から指摘される可能性があります。経費を適切に計上することは「無駄な税金を払わない」基本の節税です。 - 減価償却の活用
重機や車両など高額な設備投資は、購入した年に一括で経費化できませんが、減価償却を計画的に行うことで税金の負担を分散できます。期末の利益状況によっては「特別償却」や「即時償却制度」を活用することも検討できます。 - 小規模企業共済や倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入
共済制度は「掛け金が全額経費になる」うえ、万が一の資金繰りにも備えられるため、建設業の経営者にとって有効な節税策です。将来の退職金準備や取引先倒産リスクへの対応にも役立ちます。
キャッシュフロー改善のヒント
建設業は「入金が遅く、支払いが先」という特徴があるので、どうしても資金繰りが厳しくなりがちです。
そこでおすすめしたいのが、工事ごとに収支をきちんと管理すること。
黒字の工事と赤字の工事を把握しておくことで、「次の工事の見積もり」にも活かせます。
加えて、金融機関との関係づくりもキャッシュフローを安定させる大切なポイントです。
いざという時にスムーズに融資を受けられるよう、日頃から実績や数字を整えておくと安心ですよ。
- 入金サイトと支払サイトの見直し
工事代金の入金が遅れる一方で、外注費や材料費の支払いは早いと、資金繰りが苦しくなります。元請けとの契約条件の交渉や、外注先との支払い条件調整を行うことで、手元資金の余裕を確保できます。 - 工事ごとの収支管理
案件ごとに収益性を把握することで、「利益が出ている工事」と「赤字工事」を明確にしやすくなります。特に工期の長い工事では、途中での収支確認が資金ショート防止につながります。 - 金融機関との関係づくり
建設業は資金の流れが大きいため、いざという時に借入がスムーズにできるよう、日頃から金融機関と良好な関係を築いておくことも大切です。日常的に試算表を見せる、事業計画を共有するといった姿勢が信頼につながります。
「節税」と「キャッシュフロー改善」は、どちらも毎日の経営に直結する大事なテーマです。少しずつ取り組むことで、「税金で損をしない」「お金が回る」会社づくりにつながります。
建設業の会計・税務で専門家に相談すべきタイミング

「税理士に相談するのは、決算のときだけでいい」と思っていませんか?
実際には、建設業は他の業種よりも会計処理や税務申告が複雑で、思わぬところで資金繰りや税金に影響が出やすい業界です。
そのため、「まだ大丈夫」と放っておくと、あとで慌てるケースも少なくありません。
ここでは、特に建設業の方が税理士などの専門家に相談した方が安心できるタイミングをご紹介します。
①創業・会社設立のとき
建設業を始める際には、事業計画の作成や資金調達、許認可の取得などやるべきことがたくさんあります。
この段階で専門家に相談すれば、最適な法人形態の選び方や、創業融資のサポート、初年度からの会計体制づくりを一緒に考えてもらえます。
スタートでつまずかないことが、事業を長く続けるための大きなポイントです。
②工事規模が大きくなったとき
「最近、大きな工事を受注することが増えてきた」
そんなときは、資金繰りや原価管理の仕組みを見直すサインです。
工事が大きくなるほど入出金のタイミングのズレも大きくなり、会計処理の誤りや資金ショートのリスクも高まります。
早めに専門家に相談して、仕組みを整えておくことが安心につながります。
③決算や税務申告を迎えるとき
建設業の決算は「未成工事支出金」や「完成工事未収入金」など、業界特有の勘定科目をきちんと処理する必要があります。
ここを誤ると、税金が過大に計算されたり、逆に税務調査で指摘を受けたりする可能性があります。
「決算が近づいてきて心配…」と思ったら、早めに専門家に声をかけておくのがおすすめです。
④税務調査の通知が来たとき
建設業は現金取引や外注費が多いため、税務調査で重点的にチェックされやすい業種です。
通知が届いたら、自分だけで対応するよりも専門家に立ち会ってもらう方が安心です。
経験のある税理士なら、よくある指摘ポイントを踏まえて、スムーズに対応できるようサポートしてくれます。
⑤節税や資金繰りを考え始めたとき
「少しでも税金を抑えたい」「キャッシュフローを改善したい」
そう思ったときこそ専門家に相談する絶好のタイミングです。
設備投資や経費計上の工夫、助成金や補助金の活用など、建設業に合った具体的な提案を受けられるので、経営の選択肢がぐっと広がります。
「もっと早く相談しておけばよかった」と後悔される方は意外と多いものです。
不安を感じたときや、経営の節目を迎えたときには、遠慮なく専門家に相談することが、建設業経営を安定させる近道になりますよ。
\無料相談実施中です☺/
まとめ
建設業の税務・会計は、一般業種と比べて「工事ごとの収支管理」や「工事進行基準」など、特有のルールや注意点が多く存在します。
日々の経理処理から決算・申告、さらに税務調査や資金繰りまで、一つひとつの判断が会社の信頼や経営基盤に直結するため、「何となく」で進めるのはとても危険です。
この記事でご紹介したように、建設業には独自の実務ポイントや税務調査でよく見られる指摘事項があります。
また、キャッシュフロー改善や節税の工夫をすることで、より安定した経営につなげることも可能です。
ただし、現場の仕事と並行してこれらを完璧にこなすのは簡単ではありません。
「これって大丈夫かな?」「この処理はどうすればいいんだろう?」と不安に思ったときが、まさに専門家に相談すべきタイミングです。
税務や会計の正しい対応は、会社の成長と安定経営のための大切な基盤。
ぜひ安心して相談できる専門家とつながり、強い経営体制を築いてくださいね。
もし、
「うちの経理や税務も見てもらいたいな…」
「資金繰りや節税についてもっと知りたい」
という方は、税理士法人ストラテジーの無料相談をご利用ください!
建設業のサポート実績も豊富なので、きっとあなたの会社に合わせた具体的なアドバイスが得られるはずです。
\無料相談実施中です☺/
\無料でご相談いただけますのでお気軽にご連絡ください☺/