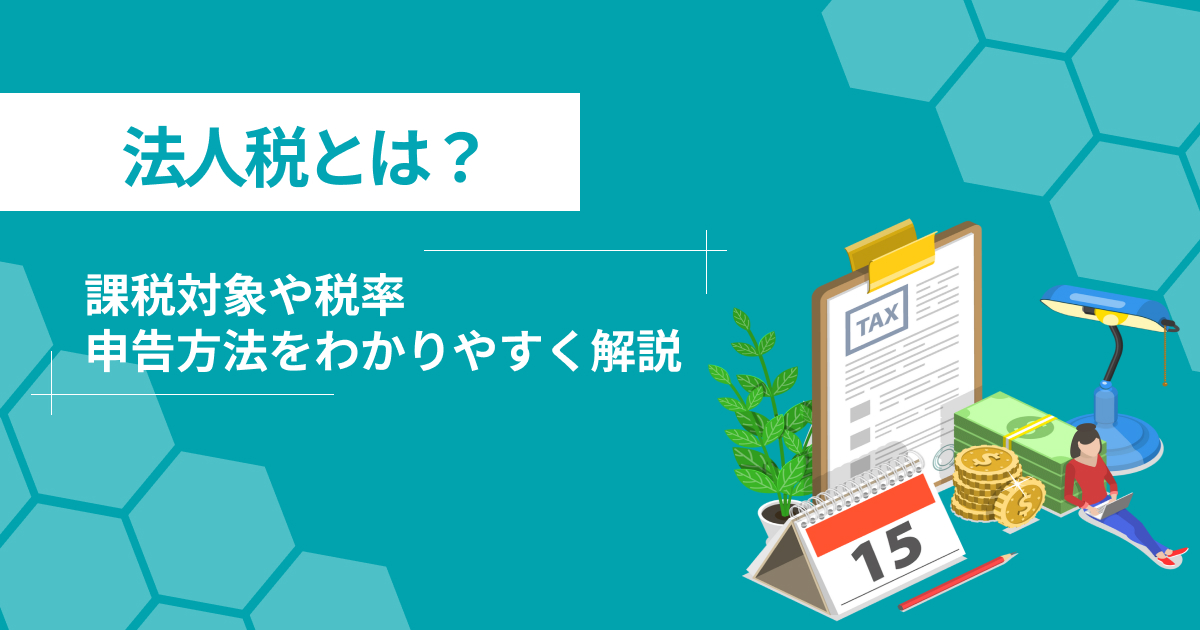法人税は、会社などの法人が事業活動で得た利益に対して課税される国税です。株式会社や合同会社を経営している方にとって、法人税の仕組みを理解することは健全な経営を行う上で欠かせません。
本記事では、法人税の基本的な仕組みから計算方法、申告手続き、節税対策まで、初めて法人税に触れる方にもわかりやすく解説します。特に中小企業の経営者や起業を検討している方に向けて、実務で役立つ情報を体系的にまとめました。
法人税とは法人が得た所得に対して国が課税する制度
法人税は、株式会社や合同会社などの法人が1年間の事業活動を通じて得た所得(利益)に対して課される国税です。
法人税の最大の特徴は、利益に対してのみ課税される点です。つまり、売上が大きくても経費がかさんで赤字になった場合は、原則として法人税はかかりません。これは事業リスクを負って経済活動を行う法人に配慮した仕組みといえるでしょう。
日本の法人税は、国が徴収する「法人税」のほか、地方自治体が徴収する「法人住民税」と「法人事業税」を合わせた3つで構成されています。これらを総称して「法人税等」と呼ぶことが一般的です。財務省によると、現在の法人税の基本税率は23.2%ですが、中小企業には軽減税率が適用され、年間所得800万円以下の部分は15%が適用され、令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されました。ただし、所得が10億円を超える事業年度は17%に引き上げられます。
法人税の歴史を振り返ると、明治32年(1899年)に創設されて以来、日本の経済発展とともに制度が整備されてきました。戦後の高度経済成長期には税率が高く設定されていましたが、グローバル競争の激化に伴い、企業の国際競争力を維持するため段階的に引き下げられてきた経緯があります。ただし、令和7年度改正で「防衛特別法人税」が創設され、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から、法人税額から500万円を控除した残額に対して4%の付加税が課されます。これにより実効税率は上昇する見込みです。
また、法人税は申告納税制度を採用しており、法人自らが所得金額と税額を計算して申告・納付する必要があります。これは税務署が税額を決定して通知する賦課課税制度とは異なり、法人側に正確な計算と申告の責任が求められる制度です。
それぞれ順に解説いたします。
株式会社や合同会社など法人税の課税対象となる法人
法人税の課税対象となる法人は大きく分けて「普通法人」「公益法人等」「協同組合等」「人格のない社団等」の4つに分類されます。最も一般的な普通法人には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社などが含まれます。
普通法人の中でも、株式会社は日本で最も多い法人形態です。株式を発行して資金調達ができ、株主の責任が出資額に限定される有限責任であることから、多くの事業者に選ばれています。一方、合同会社は2006年の会社法改正で新設された比較的新しい法人形態で、設立費用が安く、経営の自由度が高いことから、近年では起業時の選択肢として人気が高まっています。
公益法人等には、学校法人、宗教法人、社会福祉法人などが含まれ、収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。たとえば、学校法人が教育事業で得た収入は非課税ですが、駐車場経営など収益事業を行った場合、その部分については法人税が課されます。
協同組合等は、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫などが該当し、組合員の相互扶助を目的とした法人です。これらの法人は特別な税率が適用される場合があります。
人格のない社団等とは、法人格を持たないものの、団体として活動している組織を指します。たとえば、マンションの管理組合やPTA、同窓会などが該当し、収益事業を行う場合には法人税の課税対象となります。
法人税は社会保障や公共インフラの財源として使われる
財務省が発表している財政統計の通り、法人税は国の重要な財源の一つであり、令和6年度予算では約13.9兆円の税収が見込まれており、国税収入全体の約19%を占め、所得税、消費税と並ぶ基幹税として位置づけられています。
徴収された法人税は、一般会計に組み入れられ、社会保障費、公共事業費、教育費、防衛費など、国民生活に欠かせないさまざまな分野で活用されています。
特に近年では、少子高齢化に伴う社会保障費の増大が課題となっており、法人税収の安定的な確保が重要視されています。令和7年度税制改正では、防衛力強化のための財源確保として「防衛特別法人税」が創設され、令和8年4月1日以降開始の事業年度から法人税額に対して4%の付加税が課されることになりました(法人税額から500万円控除)。
また、法人税は経済政策の重要なツールとしても機能しています。景気が過熱している時期には税率を上げて企業活動を抑制し、不況時には減税や投資促進税制などで企業の投資意欲を刺激するなど、経済の安定化に寄与しています。
国際的な観点から見ると、法人税率は企業の立地選択に影響を与えるため、各国が競争的に税率を設定する傾向があります。日本も国際競争力を維持するため、段階的に法人税率を引き下げてきましたが、同時に課税ベースの拡大を図ることで、税収の確保と企業活動の活性化のバランスを取っています。
法人税と所得税の違いは納税者と課税対象にある
法人税と所得税は、どちらも「所得」に対して課税される税金ですが、納税者と課税対象、計算方法などに大きな違いがあります。
最も基本的な違いは納税者です。法人税は株式会社や合同会社などの法人が納税者となるのに対し、所得税は個人が納税者となります。たとえば、会社員の給料には所得税がかかり、その会社自体の利益には法人税がかかるという関係になります。
課税対象の範囲も異なります。所得税は給与所得、事業所得、不動産所得など10種類の所得区分があり、それぞれ異なる計算方法が定められています。一方、法人税は法人のすべての事業活動から生じた所得を一括して課税対象とし、益金から損金を差し引いて課税所得を計算します。
税率体系にも違いがあります。所得税は累進課税制度を採用しており、所得が多いほど税率が高くなります(5%から45%の7段階)。これに対し、法人税は比例税率(フラットタックス)が基本で、資本金1億円以下の中小企業を除き、所得金額にかかわらず一定の税率(23.2%)が適用されます。
また、所得控除の仕組みも異なります。所得税では基礎控除、配偶者控除、扶養控除など個人の生活事情に配慮した各種控除がありますが、法人税にはこうした控除制度はありません。代わりに、事業に必要な経費を幅広く損金として認める仕組みになっています。
さらに、課税期間にも違いがあります。所得税は暦年(1月1日から12月31日)が課税期間ですが、法人税は各法人が定めた事業年度(決算期)に基づいて課税されます。
法人税の計算方法は利益から経費を引いて税率をかける
法人税の計算は、企業会計上の利益をベースに、税法上の調整を加えて課税所得を算出し、これに税率を乗じて税額を計算するという流れで行われます。基本的な計算式は「課税所得×税率=法人税額」ですが、実際の計算プロセスはもう少し複雑です。
まず出発点となるのは、決算書上の「税引前当期純利益」です。これは企業会計の原則に従って計算された利益ですが、税法上の所得とは必ずしも一致しません。なぜなら、会計と税法では収益や費用の認識基準が異なる場合があるからです。
たとえば、交際費は会計上は全額費用として計上できますが、税法上は一定の限度額を超える部分は損金に算入できません。資本金1億円以下の中小企業の場合、年間800万円まで、または接待飲食費の50%までのいずれか多い金額まで損金算入が認められています。
また、減価償却費についても、会計上の償却方法と税法上の償却方法が異なる場合があります。会計では定額法を採用していても、税法では定率法での計算が認められているケースもあり、この差額は「申告調整」として処理されます。
寄附金についても制限があります。国や地方公共団体への寄附金は全額損金算入できますが、一般の寄附金については資本金等の額と所得金額を基準とした限度額が設けられています。
これらの調整項目を加減算して算出された「課税所得」に、法人の規模や種類に応じた税率を適用します。資本金1億円以下の中小企業については、年間所得800万円以下の部分に15%の軽減税率が適用され、それを超える部分には23.2%の税率が適用されます。
さらに、研究開発税制や設備投資促進税制などの税額控除制度を活用できる場合は、計算された法人税額から一定額を控除するできます。これらの制度は、企業の研究開発や設備投資を促進するための政策的な措置として設けられています。
それぞれ順に解説いたします。
売上から必要経費を引いた金額が課税所得として扱われる
法人税の課税所得は、簡単に言えば「益金(収益)-損金(費用)」で計算されますが、実務ではより詳細な計算が必要です。益金には売上高のほか、受取利息、受取配当金、固定資産の売却益などが含まれます。一方、損金には売上原価、販売費及び一般管理費、支払利息などが含まれます。
売上高の計上時期は、原則として商品の引渡しやサービスの提供が完了した時点です。これを「実現主義」といい、代金の回収時期とは関係なく収益を認識します。たとえば、3月決算の会社が3月に商品を納品し、代金を4月に受け取る場合でも、3月の売上として計上する必要があります。
必要経費として損金に算入できる費用には、仕入原価、人件費、地代家賃、水道光熱費、通信費、広告宣伝費、旅費交通費などがあります。ただし、これらの費用が損金として認められるためには、「事業に関連する支出であること」「通常必要と認められる金額であること」という要件を満たす必要があります。
特に注意が必要なのは、役員報酬の取り扱いです。役員報酬を損金算入するためには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当する必要があり、期中での恣意的な増減は認められません。これは、利益操作を防止するための規定です。
また、減価償却資産の取得価額についても注意が必要です。10万円未満の少額資産は全額損金算入できますが、10万円以上20万円未満の資産は3年間で均等償却、20万円以上の資産は法定耐用年数に応じて償却することになります。ただし、青色申告法人である中小企業は、30万円未満の減価償却資産について、年間300万円を限度として全額損金算入できる特例があります。
赤字の場合は法人税の一部が免除され繰越控除の適用も可能
事業年度が赤字(欠損)となった場合、その年度の法人税は原則として発生しません。さらに、青色申告法人であれば、その赤字(欠損金)を翌年度以降に繰り越して、将来の黒字と相殺できます。これを「欠損金の繰越控除」といいます。
欠損金の繰越期間は10年間です(平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金の場合)。たとえば、初年度に1,000万円の赤字が発生し、翌年度に600万円の黒字となった場合、前年度の赤字1,000万円のうち600万円を使って相殺し、翌年度の課税所得をゼロにできます。残りの400万円の赤字は、さらに翌年度以降に繰り越せます。
ただし、資本金1億円を超える大企業については、繰越控除に制限があります。具体的には、各事業年度の所得金額の50%までしか欠損金を使用できません。これは、大企業の過度な節税を防ぐための措置です。
また、「欠損金の繰戻還付」という制度もあります。これは、前年度が黒字で法人税を納付していた場合、当年度の赤字と前年度の黒字を相殺して、前年度に納付した法人税の還付を受けられる制度です。ただし、この制度は資本金1億円以下の中小企業等に限定されています。
赤字であっても、会計上の赤字と税務上の赤字が異なる場合があることにも注意が必要です。たとえば、交際費の損金不算入額や寄附金の損金不算入額がある場合、会計上は赤字でも税務上は黒字となり、法人税が発生する可能性があります。
赤字でも法人住民税の均等割など一部の税金は発生する
法人が赤字の場合、法人税(国税)は発生しませんが、地方税である法人住民税の均等割は、利益の有無にかかわらず必ず納付する必要があります。均等割は、法人が地方自治体から受ける行政サービスの対価という性格を持つため、赤字でも負担が求められます。
法人住民税の均等割額は、資本金等の額と従業員数によって決まります。たとえば、東京23区内に本店を置く資本金1,000万円以下、従業員50人以下の法人の場合、都民税均等割が年額7万円となります。この金額は自治体によって異なり、市町村民税と都道府県民税を合わせると、最低でも年額7万円程度の負担が生じます。
また、法人事業税についても、一部の自治体では「付加価値割」や「資本割」といった外形標準課税が適用される場合があります。これらは資本金1億円超の法人に適用されることが多いですが、赤字でも課税される仕組みです。
中小企業と大企業では適用される法人税率が異なる
日本の法人税制では、中小企業の税負担を軽減するため、大企業と異なる優遇措置が設けられています。最も代表的なのが軽減税率の適用です。
資本金1億円以下の中小法人については、年間所得800万円以下の部分に対して15%の軽減税率が適用されます(令和7年度税制改正により、所得10億円超の場合は17%に引き上げ、適用期間を2年延長)。これに対し、資本金1億円超の大企業や、所得800万円を超える部分については、一律23.2%の税率が適用されます。
たとえば、年間所得が1,000万円の中小企業の場合、800万円×15%=120万円、200万円×23.2%=46.4万円で、合計166.4万円の法人税となります。仮に全額に23.2%が適用されると232万円となるため、65.6万円の軽減効果があります。
ただし、すべての中小企業が軽減税率の適用を受けられるわけではありません。大企業の100%子会社など、実質的に大企業と同視できる法人は適用対象外となります。また、令和7年度税制改正により、グループ通算制度の適用を受けている法人も除外されることになりました。
中小企業にはその他にもさまざまな優遇措置があります。たとえば、中小企業投資促進税制では、一定の設備投資を行った場合に特別償却や税額控除が受けられます。
法人税の支払い方法4つを紹介!期限を守るために知っておこう
法人税の納付は、決算日から2カ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると延滞税などのペナルティが課されます。納付方法は複数用意されており、それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて選択することが重要です。
法人税の納付には、「中間申告・中間納付(予定申告)」と「確定申告・確定納付」の2種類があります。中間申告は、前年度の法人税額が20万円を超える場合に、事業年度開始から6カ月を経過した日から2カ月以内に、前年度実績の半分相当額を納付する制度です。これにより、年度末の納税負担を分散させられます。
確定納税は、決算確定後に正確な税額を計算して納付するもので、予定納税を行っている場合は、その差額を精算します。予定納税額が確定税額を上回った場合は、還付を受けられます。
納付期限を守ることは極めて重要です。1日でも遅れると延滞税が課され、納付すべき税額に対して年8.7%(最初の2カ月間は年2.4%)の割合で計算されます(特例基準割合に基づく)。また、無申告の場合はさらに重い無申告加算税も課されるため、資金繰りが厳しい場合でも、まずは申告だけは期限内に行うことが大切です。
最近では、デジタル化の進展により、オンラインでの納付方法が充実してきました。24時間対応可能な方法も増え、締切直前でも対応できるようになっています。ただし、システムメンテナンスなどで利用できない時間帯もあるため、余裕を持った納付計画を立てることが重要です。
また、納付方法によっては領収証書が発行されない場合もあります。税務調査などに備えて、納付の記録を適切に保管しておく必要があります。電子納付の場合は、納付完了画面の印刷やスクリーンショットを保存しておくことをおすすめします。
それぞれ順に解説いたします。
クレジットカード納付は手数料がかかるが手続きが簡単
クレジットカード納付は、国税庁が提供する「国税クレジットカードお支払サイト」を通じて、24時間いつでも納付できる便利な方法です。インターネット環境があれば、自宅やオフィスから簡単に手続きができ、現金を用意する必要もありません。
最大のメリットは、カード会社への支払いを分割払いやリボ払いにすることで、実質的に納税の時期を遅らせられる点です。資金繰りが厳しい時期には、この仕組みを活用することで、一時的な資金不足を解消できる可能性があります。また、カード会社のポイントが付与される場合もあり、実質的な納税負担を軽減できることもあります。
ただし、デメリットとして手数料がかかることに注意が必要です。納付税額に応じた決済手数料が発生し、たとえば1万円超2万円未満で198円、以降段階的に増加(約0.99%相当)。100万円の場合、約9,900円程度の手数料がかかります。この手数料は経費として損金算入できますが、それでも追加コストであることに変わりはありません。
また、利用限度額にも注意が必要です。1回の手続きで納付できる上限は1,000万円未満で、かつクレジットカードの利用可能額の範囲内となります。大口の納税には向かない場合があるため、事前に確認が必要です。
e-Taxを使えば法人税をオンラインで納付することができる
e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、インターネットを通じて国税の申告や納付ができるシステムです。法人税の電子納付には「ダイレクト納付」と「インターネットバンキング納付」の2つの方法があります。
ダイレクト納付は、事前に税務署に届出をしておくことで、e-Taxから直接預貯金口座から振替納付ができる仕組みです。手数料が無料で、納付日を指定できるため、資金繰りの計画が立てやすいというメリットがあります。また、複数の税目をまとめて納付することも可能です。
インターネットバンキング納付は、金融機関のインターネットバンキングを利用して納付する方法です。Pay-easy(ペイジー)に対応している金融機関であれば利用可能で、こちらも手数料はかかりません。ただし、各金融機関のインターネットバンキングの契約が必要となります。
e-Taxを利用するためには、事前準備として電子証明書の取得やe-Taxの利用者識別番号の取得が必要です。初期設定には多少の手間がかかりますが、一度設定してしまえば、その後は簡単に利用できます。特に、申告と納付を一連の流れで行えるため、事務効率の向上につながります。
スマホアプリ納付は手軽さが特徴で個人事業主にも人気
スマホアプリ納付は、令和4年12月から開始された比較的新しい納付方法で、PayPayやd払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、Amazon Payなどのスマホ決済アプリを使って国税を納付できます。
最大の特徴は、スマートフォンさえあれば、いつでもどこでも納付できる手軽さです。国税庁の納付サイトにアクセスし、納付情報を入力後、利用するアプリを選択してQRコードを読み取るだけで納付が完了します。アプリに事前にチャージしておけば、銀行口座やクレジットカードの情報を入力する必要もありません。
手数料が無料である点も大きなメリットです。クレジットカード納付のような決済手数料がかからないため、コストを抑えて納付できます。また、アプリによってはポイント還元やキャンペーンを実施していることもあり、お得に納付できる場合があります。
ただし、納付上限額は1回30万円であり、複数回に分けて30万円を超える納付はできません(2025年2月1日以降の取扱い)。このため法人税のような高額納付には不向きです。主に個人事業主の所得税や、中小企業の源泉所得税など、比較的少額の納税に適しています。また、領収証書は発行されないため、納付完了画面を必ず保存しておく必要があります。
銀行振込や窓口納付など従来の支払い方法も選択できる
従来からある銀行振込や金融機関・税務署の窓口納付も、依然として多くの法人に利用されている確実な納付方法です。特に高額納税や、電子的な手続きに不慣れな場合には、これらの方法が安心です。
銀行振込による納付は、納付書を使って金融機関から振り込む方法です。全国の銀行、信用金庫、信用組合などで取り扱っており、確実に納付できます。振込手数料は納税者負担となりますが、振込明細書が証拠として残るため、記録管理がしやすいというメリットがあります。
窓口納付は、現金を持参して金融機関や税務署の窓口で直接納付する方法です。その場で領収証書が発行されるため、納付の証拠が即座に手に入ります。ただし、窓口の営業時間内(通常平日9時~15時)に行く必要があり、待ち時間が発生することもあるため、時間的な制約があります。
コンビニ納付も可能ですが、バーコード付き納付書が必要で、納付額が30万円以下の場合に限られます。24時間納付可能で、身近なコンビニで手続きできる利便性はありますが、法人税のような高額納税には適していません。
これらの従来型の納付方法は、インターネット環境やシステムトラブルに左右されない確実性があります。特に納付期限が迫っている場合や、電子納付の設定が間に合わない場合には、窓口納付が最も確実な方法といえるでしょう。
法人税の節税には計画的な対策が必要!代表的な方法を紹介
法人税の節税は、適法な範囲で税負担を軽減する重要な経営戦略です。ただし、場当たり的な対策では効果が限定的になるため、年間を通じた計画的な取り組みが必要です。節税対策は大きく分けて、「税額控除の活用」「損金算入の最大化」「課税の繰り延べ」の3つのアプローチがあります。
節税対策を検討する際は、まず自社の財務状況と将来の事業計画を正確に把握することが重要です。たとえば、今期は大幅な黒字が見込まれるが来期は設備投資で赤字予想という場合と、安定的に黒字が続く見込みの場合では、取るべき対策が異なります。
また、節税だけを目的とした不必要な支出は、かえって企業の財務体質を悪化させる可能性があります。たとえば、節税のために不要な備品を購入しても、法人税率が23.2%であれば、100万円の支出に対して節税効果は23.2万円に過ぎません。残りの76.8万円は純粋な支出となるため、本当に必要な投資かどうかを慎重に判断する必要があります。
節税対策は、単年度の税負担軽減だけでなく、中長期的な企業価値向上につながるものを選択することが大切です。研究開発や人材育成、設備の近代化など、将来の競争力強化につながる投資は、節税効果と事業成長の両方を実現できる理想的な対策といえるでしょう。
それぞれ順に解説いたします。
税額控除や特別償却など制度を活用した節税策がある
税額控除と特別償却は、国が政策的に設けている節税制度で、要件を満たせば大きな節税効果が期待できます。これらの制度は、企業の積極的な投資や研究開発を促進することを目的としています。
研究開発税制(研究開発費の税額控除)は、最も活用されている制度の一つです。試験研究費の8~14%(中小企業は12~17%)を法人税額から直接控除できます。たとえば、年間1,000万円の研究開発費を支出した中小企業の場合、最大170万円の税額控除を受けられる可能性があります。対象となる試験研究費には、研究員の人件費、原材料費、外部委託費なども含まれます。
中小企業投資促進税制では、機械装置などの設備投資を行った場合、取得価額の7%の税額控除か30%の特別償却を選択できます。さらに、中小企業経営強化税制を活用すれば、即時償却(100%償却)や10%の税額控除も可能です。令和7年度からは、売上高100億円超を目指すなど事業規模拡大を目指す中小企業向けの措置も追加されました。
賃上げ促進税制も注目の制度です。前年度から給与等支給額を一定割合以上増加させた場合、増加額の15~40%を税額控除できます。人材確保が課題となっている現在、賃上げによる人材定着と節税を同時に実現できる制度として活用が進んでいます。
雇用促進税制では、雇用者数を一定以上増加させた場合に税額控除を受けられます。地方創生に資する企業の地方拠点強化税制と組み合わせることで、さらなる優遇を受けることも可能です。
経費として計上できる支出を正しく処理することも重要
適正な経費計上は、最も基本的かつ重要な節税対策です。事業に必要な支出を漏れなく経費として計上することで、課税所得を適正に圧縮できます。ただし、税務調査で否認されないよう、正しい処理が求められます。
まず重要なのは、領収書や請求書などの証憑書類を適切に保管することです。電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの保存も義務化されています。これらの書類は、経費の正当性を証明する重要な証拠となります。
少額減価償却資産の特例を活用することも効果的です。青色申告をしている中小企業は、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間300万円を限度として、その取得価額の全額を損金算入できます。通常は資産計上して数年かけて償却するところを、一括で経費化できるため、即効性のある節税対策となります。
出張旅費規程を整備することで、日当や宿泊費を非課税で支給できます。実費精算ではなく、規程に基づく定額支給とすることで、事務処理の簡素化と節税を同時に実現できます。ただし、社会通念上相当と認められる範囲内である必要があります。
社宅制度の活用も検討に値します。会社が借り上げた物件を役員や従業員に貸与する場合、一定の家賃を徴収すれば、会社負担分を経費計上できます。特に役員社宅は、適正な賃料計算を行えば、実質的な手取り増加と法人税の節税を両立できます。
赤字繰越や設備投資のタイミングも節税に直結する
欠損金の繰越控除制度を戦略的に活用することは、中長期的な節税対策として重要です。青色申告法人であれば、赤字を10年間繰り越せるため、創業期の赤字を将来の黒字と相殺できます。
設備投資のタイミングも節税効果に大きく影響します。決算期末近くに設備を取得しても、その期の償却費は月割計算となるため、節税効果は限定的です。期首に近いタイミングで投資を行えば、その期により多くの償却費を計上できます。また、特別償却制度を活用する場合は、適用要件や期限に注意が必要です。
在庫の評価方法の選択も重要です。最終仕入原価法、先入先出法、総平均法など複数の方法があり、物価動向によって有利な方法が異なります。一度選択した方法は継続適用が原則ですが、合理的な理由があれば変更も可能です。
決算期の変更も選択肢の一つです。季節変動が大きい事業の場合、繁忙期を決算期にすると利益が大きくなりがちです。閑散期を決算期にすることで、在庫を減らし、経費を適切に計上しやすくなります。ただし、決算期変更には定款変更や税務署への届出が必要で、変更した期は変則決算となることに注意が必要です。
法人税の申告手続きについて解説
法人税の申告は、事業年度終了後2カ月以内に行う必要があり、正確な申告書の作成と期限内の提出が求められます。申告手続きは複雑で専門知識が必要なため、多くの企業が税理士に依頼していますが、基本的な流れを理解しておくことは経営者にとって重要です。
申告書類は、法人税申告書(別表)と添付書類で構成されます。別表は全部で20種類以上ありますが、すべての法人が提出する必要があるのは別表一(確定申告書)、別表二(同族会社等の判定に関する明細書)、別表四(所得の金額の計算に関する明細書)、別表五(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)などです。
添付書類としては、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表などの決算書類が必要です。さらに、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書なども提出します。これらの書類は、会社の財務状況を詳細に示すもので、税務調査の際の基礎資料となります。
申告書の作成にあたっては、会計上の利益と税務上の所得の調整(申告調整)が最も重要かつ複雑な作業となります。交際費の損金不算入、寄附金の損金算入限度額計算、減価償却の調整など、多くの調整項目があり、それぞれ正確に計算する必要があります。
電子申告(e-Tax)の利用が年々増加しており、大法人については電子申告が義務化されています。中小企業も電子申告を利用することで、申告書の提出が24時間可能になる、税務署への訪問が不要になる、データの再利用が可能になるなどのメリットを享受できます。
申告期限を過ぎてしまった場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。やむを得ない事情がある場合は、申告期限の延長申請を行うこともできますが、原則として災害などの特別な事情に限られます。資金繰りの都合で納税が困難な場合でも、まずは申告だけは期限内に行い、納税については猶予申請を検討することが重要です。
それぞれ順に解説いたします。
青色申告と白色申告の違いは記帳要件や控除の有無にある
法人の申告方法には青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれ異なる要件と特典があります。現在、ほとんどの法人が青色申告を選択していますが、その理由は青色申告の税務上のメリットが大きいためです。
青色申告の最大のメリットは、欠損金の繰越控除です。青色申告法人は赤字を10年間繰り越して将来の黒字と相殺できますが、白色申告法人にはこの特典がありません。また、欠損金の繰戻還付(前年の黒字と当年の赤字を相殺して還付を受ける制度)も青色申告法人限定です。
青色申告を行うためには、事前に「青色申告の承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。新設法人の場合は設立後3カ月以内、既存の白色申告法人が青色申告に変更する場合は、青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日までに申請が必要です。
青色申告の要件として、複式簿記による記帳と、総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿書類の作成・保存が義務付けられています。これらの帳簿は7年間(一部は10年間)保存する必要があります。電子帳簿保存法に基づく電子保存も認められており、ペーパーレス化を進めることも可能です。
その他の青色申告のメリットとして、30万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入、税額控除制度の適用、更正の制限(税務署が更正する場合は理由を明記する必要がある)などがあります。これらの特典を考慮すると、記帳の手間を差し引いても青色申告を選択する価値は十分にあります。
法人税申告書は税務署からの様式に基づいて作成する必要がある
法人税申告書は、国税庁が定める統一様式(別表)を使用して作成します。これらの様式は国税庁のホームページからダウンロードできますが、税制改正により毎年様式が変更されることがあるため、必ず最新版を使用する必要があります。
主要な別表として、別表一は申告書の本体で、課税所得金額と税額を記載します。別表四は所得金額の計算過程を示すもので、会計上の利益から税務上の所得への調整過程を詳細に記載します。この別表四の作成が申告書作成の中核となり、最も時間と専門知識を要する部分です。
別表五(一)は利益積立金額と資本金等の額の内訳を示し、過去からの累積状況を管理します。別表五(二)は租税公課の納付状況を記載し、源泉所得税や住民税などの納付・未納状況を明確にします。これらの別表は相互に関連しており、一つでも誤りがあると全体の整合性が取れなくなります。
勘定科目内訳明細書も重要な添付書類です。預貯金、売掛金、買掛金、借入金などの内訳を取引先別に記載し、決算書の各勘定科目の詳細を明らかにします。税務調査では、この内訳書を基に取引の実態を確認されることが多いため、正確な作成が求められます。
法人事業概況説明書は、会社の事業内容、従業員数、主要取引先、月別売上高などを記載する書類で、税務署が会社の概要を把握するための重要な資料となります。虚偽記載は罰則の対象となるため、事実に基づいて正確に記載する必要があります。
申告は決算から2カ月以内!遅れる前に余裕を持って対応を
法人税の確定申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内と定められています。たとえば、3月決算の会社は5月31日が申告期限となります。この期限は厳格に運用され、1日でも遅れると無申告加算税や延滞税が課されます。
申告期限の延長が認められるケースは限定的です。災害などやむを得ない理由がある場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請」を行えます。また、会計監査人の監査を受ける必要がある法人は、定款に定めることで1カ月の延長が認められますが、これは申告期限の延長であり、納付期限は延長されない点に注意が必要です。
決算作業から申告までのスケジュール管理が重要です。一般的な流れとして、決算日後1カ月で決算数値を確定し、その後1カ月で申告書を作成・提出します。しかし、実際には株主総会の開催や、申告調整の複雑さから、期限ぎりぎりになることが多いのが実情です。
期限に遅れた場合のペナルティは重大です。無申告加算税は、原則として納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%)が課されます。さらに延滞税も加算され、納付が遅れるほど負担が増大します。税務調査で無申告が発覚した場合は、さらに重い35~40%の重加算税が課される可能性もあります。
申告手続きは紙による提出と電子申告の2通りがある
- 従来からの書面提出
- インターネットを利用した電子申告(e-Tax)
法人税の申告方法には、従来からの書面提出と、インターネットを利用した電子申告(e-Tax)の2つがあります。資本金1億円超の大法人は電子申告が義務化されていますが、中小企業は任意で選択できます。
書面提出の場合、作成した申告書と添付書類を税務署の窓口に持参するか、郵送で提出します。窓口提出の場合は、受付印を押印した控えをその場で受け取れるため、提出の証拠が明確に残ります。郵送の場合は、消印の日付が提出日となるため、期限日の締切時間を気にする必要がありませんが、控えが必要な場合は返信用封筒を同封する必要があります。
電子申告は、24時間365日(メンテナンス時間を除く)提出可能で、税務署に出向く必要がありません。また、添付書類の一部を省略できる、データの再利用が可能、還付金の処理が早いなどのメリットがあります。ただし、事前に電子証明書の取得や、e-Taxの利用者識別番号の取得など、初期設定が必要です。
電子申告の普及率は年々上昇しており、令和4年度には法人税申告の約90%が電子申告となっています。税理士に依頼している場合は、ほぼ確実に電子申告で提出されます。
法人税に関するよくある質問
法人税はどのタイミングで支払うのが正しいのでしょうか?
法人税の支払いタイミングは、主に「中間納付」と「確定納付」の2回です。中間納付は、前年度の法人税額が20万円を超える場合に必要で、事業年度開始から6カ月を経過した日から2カ月以内に、前年度実績の半分相当額を納付します。たとえば、3月決算法人の場合、11月30日が中間納付期限となります。
確定納付は、決算日から2カ月以内に行います。3月決算なら5月31日が期限です。中間納付を行っている場合は、確定税額から中間納付額を差し引いた金額を納付します。もし中間納付額が確定税額を上回った場合は、還付を受けられます。期限を1日でも過ぎると延滞税が発生するため、資金繰りを考慮して計画的に準備することが大切です。
中小企業と大企業では法人税の仕組みは違うのでしょうか?
中小企業と大企業では、適用される税率や利用できる優遇制度に大きな違いがあります。最も大きな違いは税率で、資本金1億円以下の中小企業は、年間所得800万円以下の部分に15%の軽減税率が適用されますが、令和7年度改正により所得10億円超の場合は17%に引き上げられます。大企業は所得金額にかかわらず一律23.2%です。
また、中小企業にはさまざまな優遇制度があります。30万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入、中小企業投資促進税制による特別償却や税額控除、欠損金の繰戻還付など、大企業には適用されない特例が多数用意されています。一方で、大企業は電子申告が義務化されているなど、コンプライアンス面での要求も高くなっています。税理士に相談する際も、中小企業特有の制度を熟知している専門家を選ぶことが重要です。
税理士に依頼せずに法人税を申告することは可能ですか?
法人税の申告を自社で行うことは法律上可能です。実際、小規模な法人の中には、経理担当者が会計ソフトを使って申告書を作成しているケースもあります。国税庁のホームページには申告書の様式や記載要領が公開されており、e-Taxを利用すれば電子申告も可能です。
ただし、実務上は多くの専門知識が必要です。会計と税務の違いを理解し、適切な申告調整を行う必要があります。また、税制は毎年改正されるため、最新の情報を把握し続ける必要があります。誤った申告をすると、税務調査で指摘を受け、追徴課税や加算税のリスクがあります。特に、税額控除や特別償却などの優遇制度は要件が複雑で、適用漏れによる機会損失も考えられます。コスト面だけでなく、正確性と効率性を総合的に判断して、税理士への依頼を検討することをおすすめします。