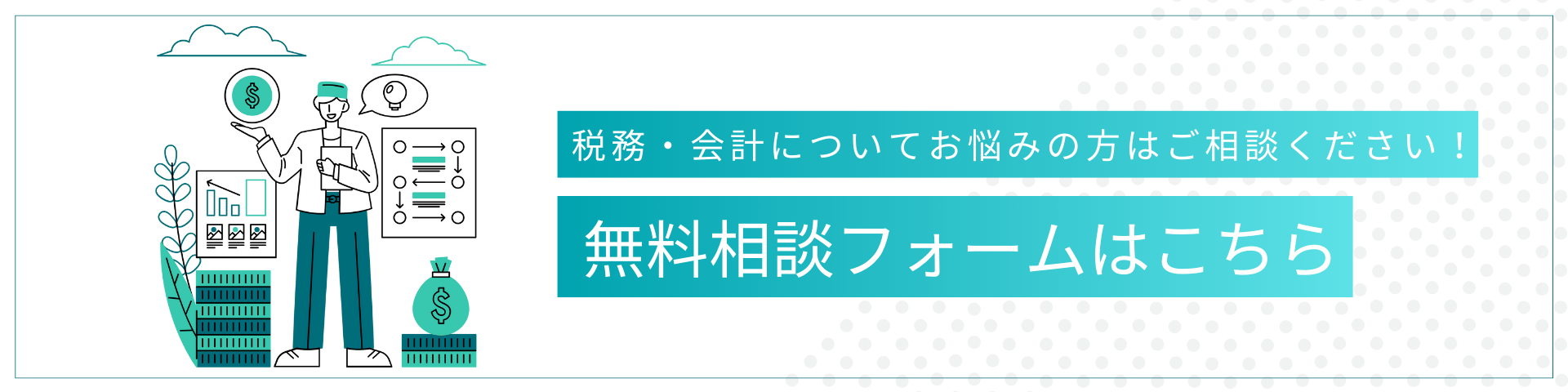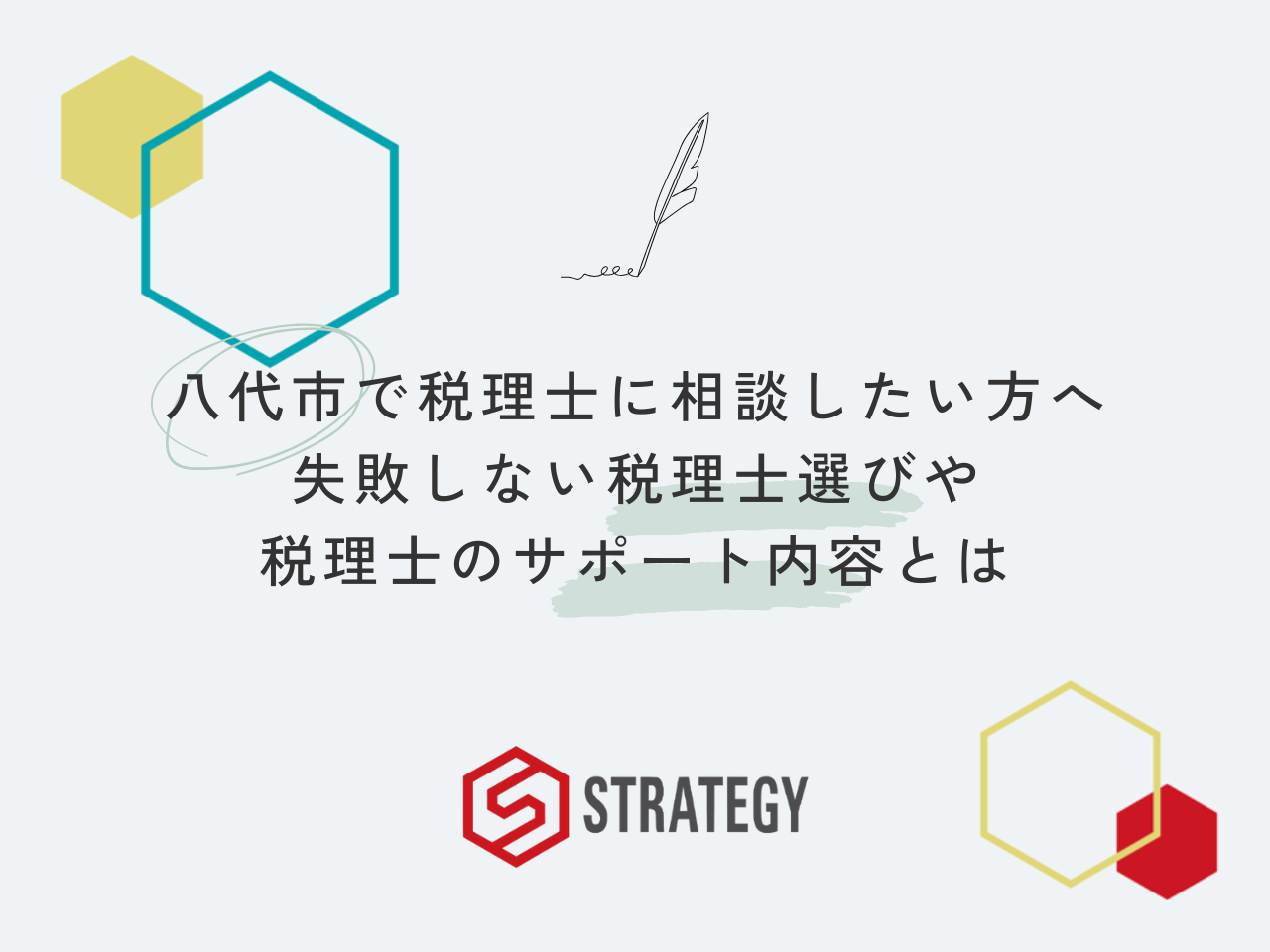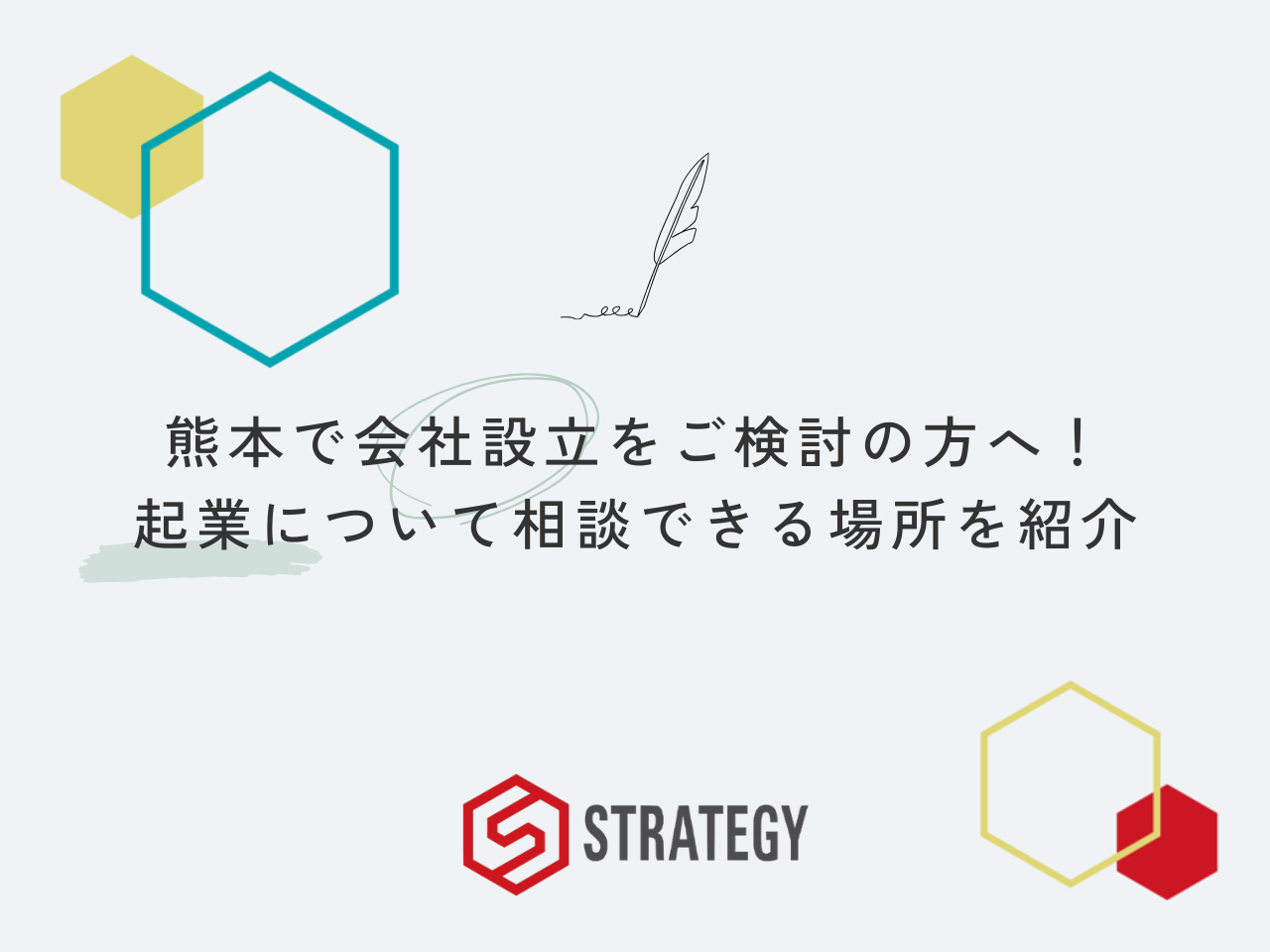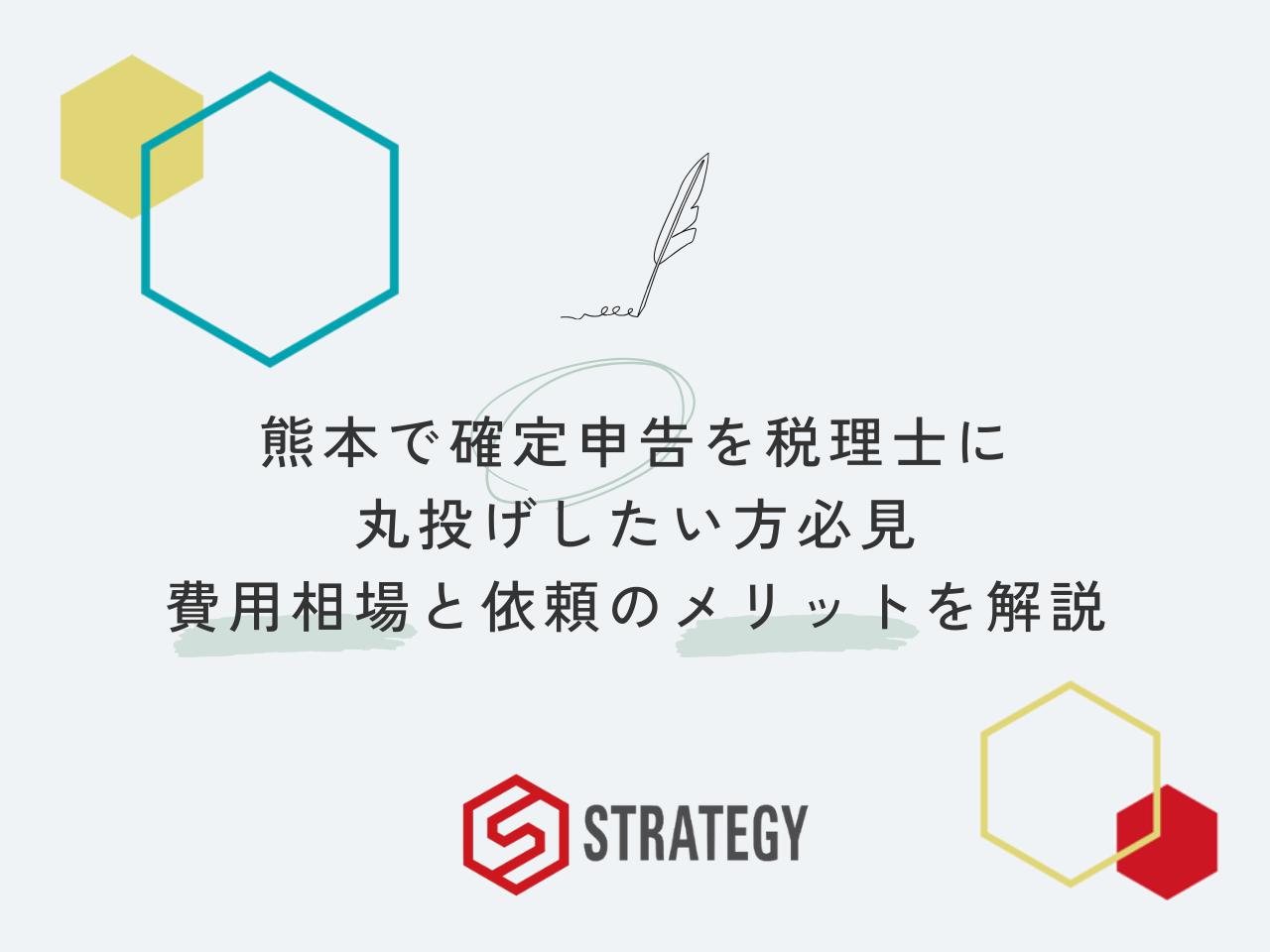税理士が教える!法人の節税対策15選|無理なく利益を守る方法
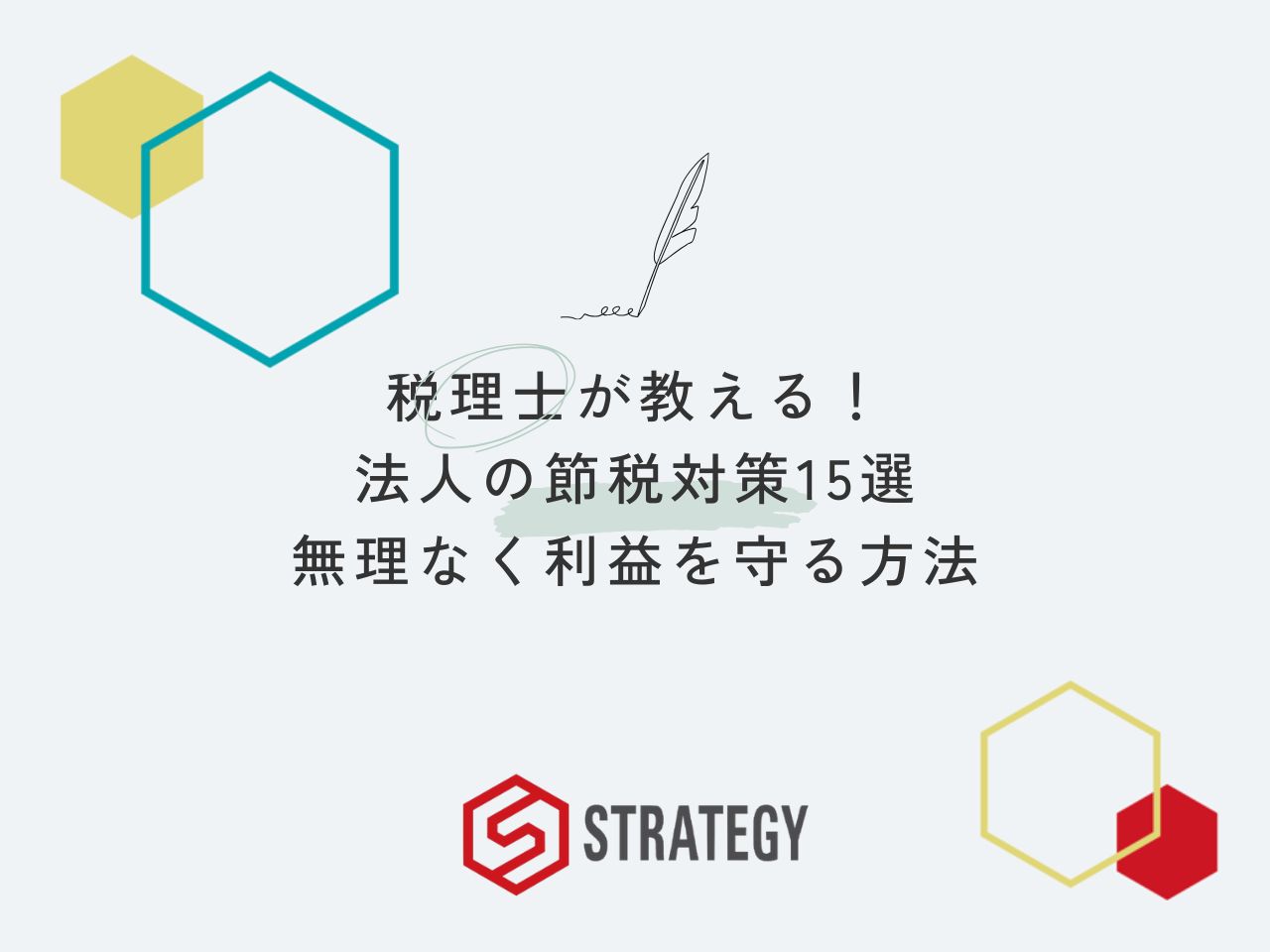
法人を経営していると、毎年の決算期になるたびに「もう少し税金を減らせないかな…?」と思うことはありませんか?
頑張って売上を上げても、税金として大きな額が出ていくと、なんだかもったいない気がしますよね。
実は、法人の節税対策には「やっていい節税」と「やってはいけない節税」があります。
節税というと「裏技のようなテクニック」を想像する方もいますが、本当に大切なのは、法律の範囲内で会社のお金の使い方を最適化すること、です。
たとえば、役員報酬の設定のしかた、福利厚生費の使い方、共済制度の活用など。
知っているかどうかで、同じ売上・同じ利益でも、手元に残るお金が大きく変わってきます。
この記事では、税理士の視点から、
- 法人が実践できる正しい節税対策
- 注意すべきNGな節税方法
- 専門家に相談するメリット
をやさしく解説します。
「難しいことは苦手だけど、会社の利益を守りたい!」
そんな経営者さんにこそ、読んでほしい内容です。
あなたの会社に合った“ムリのない節税”のヒントを、一緒に見つけていきましょう🌱
目次
1.なぜ法人に節税対策が必要なのか
1.1.法人が負担する会社の種類とは?
1.2.「節税=悪いこと」ではない!
2.税理士がすすめる法人の節税対策15選
2.1.①役員報酬の適正化
2.2.②役員退職金制度の導入
2.3.③中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の活用
2.4.④小規模企業共済の加入
2.5.⑤生命保険を利用したリスクマネジメント
2.6.⑥福利厚生費の充実
2.7.⑦決算賞与の活用
2.8.⑧貸倒引当金の設定
2.9.⑨固定資産の耐用年数・減価償却方法の見直し
2.10.⑩少額減価償却資産の特例利用
2.11.⑪交際費の上限を把握して有効活用
2.12.⑫在庫の適正管理
2.13.⑬クラウド会計を活用した経費管理の徹底
2.14.⑭青色申告特別控除を活かす(法人化前の個人事業主向け)
2.15.⑮資金繰り・投資計画と連動した節税設計
3.やってはいけない節税対策とは?
3.1.架空経費や架空取引を計上する
3.2.個人の支出を会社経費にする
3.3.保険を使った過剰な節税
3.4.無理な仕入れや在庫増で利益を調整する
3.5.節税を優先して事業投資を削る
3.6.税制改正を無視する
4.節税対策を成功させるコツ
4.1.会社の利益や資金状況を把握する
4.2.節税と成長戦略をセットで考える
4.3.複数の節税方法を組み合わせる
4.4.節税策は早めに計画する
4.5.税理士などの専門家に相談する
5.まとめ
なぜ法人に節税対策が必要なのか
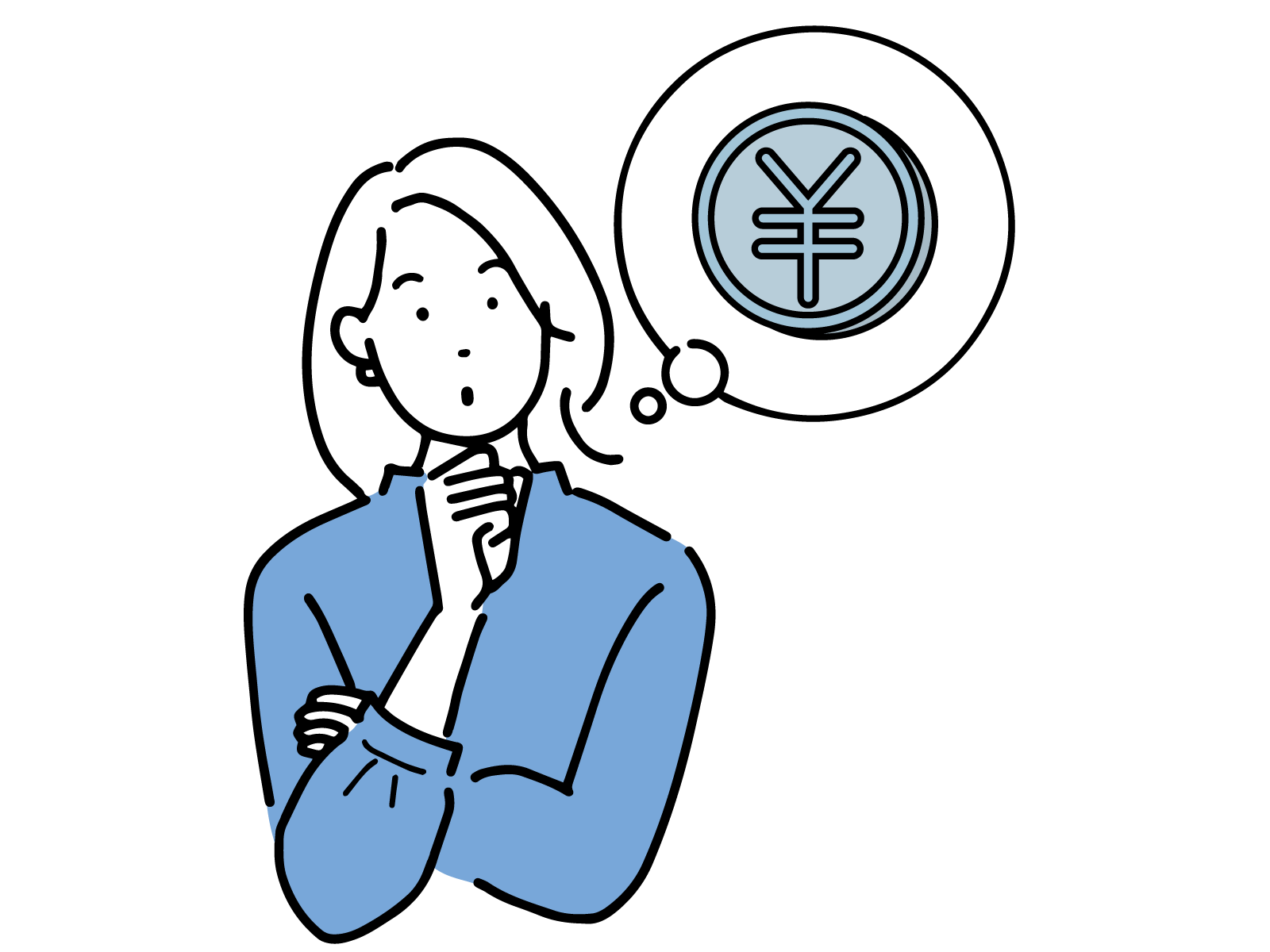
法人を運営していると、どうしても避けられないのが「税金」です。
法人税だけでなく、地方税、事業税、消費税など、さまざまな税金がかかります。
決算を迎えるたびに、「思ったより納税額が多かった…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
けれど、節税対策をしっかり行えば、同じ利益でも手元に残るお金を増やすことができます。
これは、単に「税金を減らす」ことが目的ではなく、会社をより安定させ、将来に備えるための大切な経営戦略のひとつなんです。
法人が負担する会社の種類とは?
まず、法人が負担する税金の種類を整理してみましょう。
皆様ご存知の通り、法人が支払う税金は少なくないです。
- 法人税(会社の所得に対して課税される)
- 法人住民税(都道府県・市区町村に納める)
- 法人事業税(所得に応じて課税)
- 消費税(売上が一定額を超えると発生)
さらに、従業員を雇っていれば源泉所得税や社会保険料なども関係してきます。
これらを合計すると、売上の数十%が「税金・保険料」として会社から出ていくこともあります。
税金は「利益が出たら払うもの」ですが、納税時期が資金繰りに重なると、手元資金が一気に減ってしまい、節税を怠ると「キャッシュフロー」が悪化してしまいます。
たとえば、決算で黒字になったものの、手元に現金が残っていないケース。
これは、節税を考えずに経費や支出をコントロールしていなかったことが原因であることも多いです。
節税対策を計画的に行うことで、
- 納税額を抑えつつ、
- 手元の資金を確保し、
- 将来の投資にまわせる余裕をつくる
という理想的なサイクルを作ることができます。
「節税=悪いこと」ではない!
「節税」という言葉に、なんとなく後ろめたさを感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ですが、正しい節税はまったく悪いことではありません。
むしろ、経営を安定させ、従業員や取引先を守るための“前向きな取り組み”なのです。
もちろん、架空経費の計上や脱税のような行為はNGですが、法律で認められた仕組みを正しく活用する節税は、国も推奨している「適正な経営判断」であり、「会社を育てるための投資」でもあります。
節税の本質は、「税金を減らすこと」ではなく、“将来のためにお金を残すこと” です。
たとえば、福利厚生を充実させて社員の満足度を上げたり、設備投資をして生産性を高めたり、共済制度に加入して将来の備えを作ったり…。
これらはすべて「正しい節税対策」であり、結果的に会社の成長につながる行動です。
\無料相談実施中です☺/
税理士がすすめる法人の節税対策15選
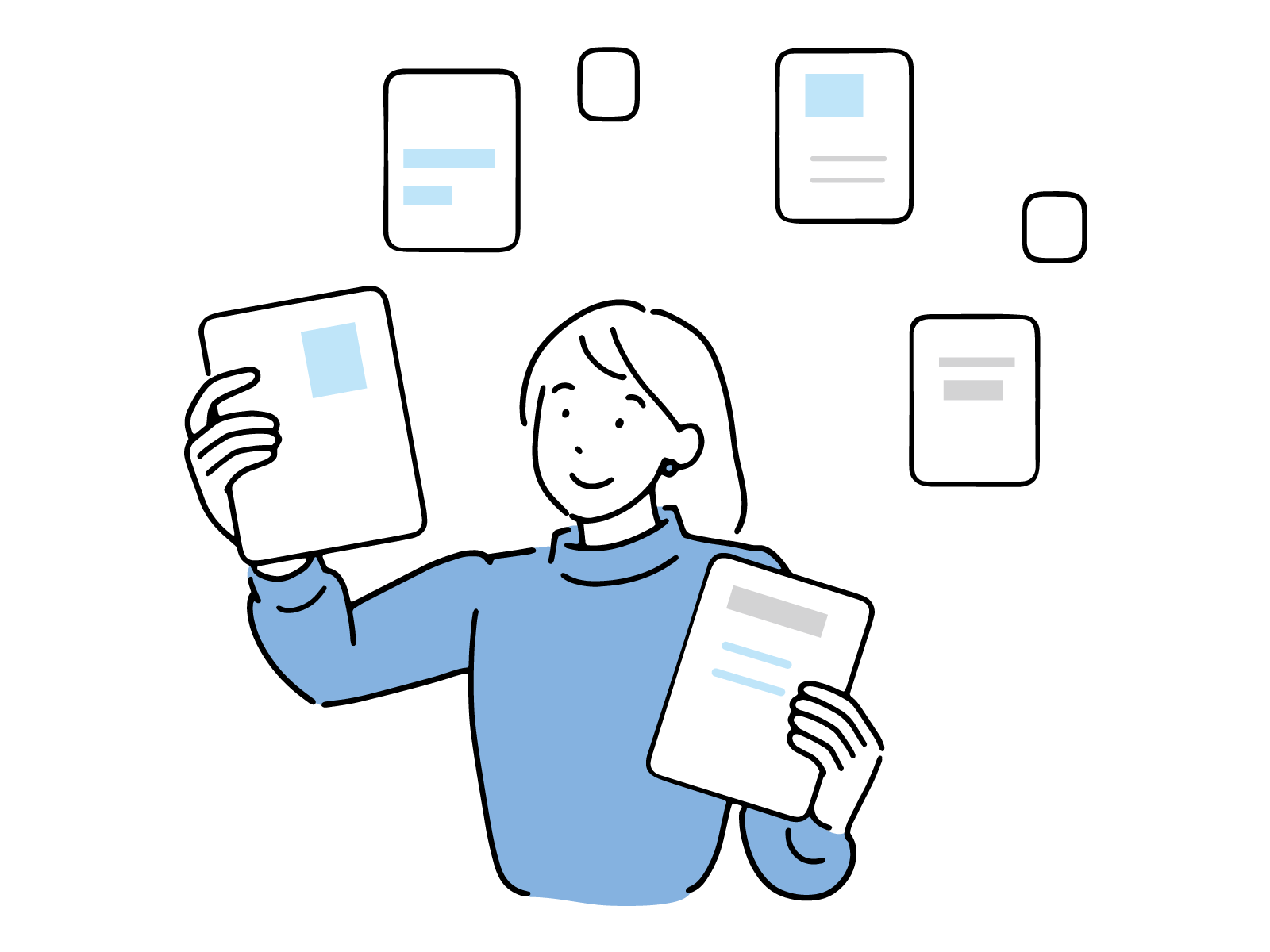
法人の節税対策は、「無駄に税金を減らす」ことではなく、会社の成長をサポートしながら、手元資金を賢く残すことが目的です。
ここでは、実際の企業でよく取り入れられている15の方法を、少し深掘りしてご紹介します。
①役員報酬の適正化
法人の利益は、役員報酬の金額によって大きく変わります。
報酬が少なすぎると会社の利益が増えて法人税が高くなり、逆に多すぎると個人の所得税が重くなってしまいます。
ポイントは、「会社と個人の両方でバランスが取れる金額」に設定すること。
決算の前に「今期の利益をどのくらいにしたいか」を確認し、報酬の見直しを行うことで、税負担をコントロールできます。
②役員退職金制度の導入
退職金は、長年会社に貢献した役員への報酬として、損金に算入できるのが大きなメリットです。
たとえば、30年間経営に携わった社長が退任する場合、数千万円単位の退職金を支給しても、適正額であれば節税効果は非常に大きくなります。
「退職金規程」を整備しておくと、将来のトラブル防止にもつながります。
③中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の活用
この制度は、取引先が倒産したときに資金を借りられる共済です。
中小企業(資本金や従業員数に応じて条件あり)、個人事業主等が加入できます。
実は掛金(月20万円まで)が全額経費になるという節税メリットもあります。
しかも、解約すれば積み立てた分が戻るため、リスクが少ないのも魅力。
「税金を減らしつつ、万が一に備える」ことができる、経営者に人気の制度です。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済とは」
④小規模企業共済の加入
こちらは、経営者自身のための“退職金準備制度”です。
掛金(月7万円まで)は全額所得控除になるため、個人の所得税・住民税の節税に直結します。
法人で働く社長さん個人としても利用できるので、「法人+個人」の両面で節税を狙えるのがポイントです。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済とは」
⑤生命保険を利用したリスクマネジメント
法人で契約する生命保険には、損金に算入できるタイプとそうでないタイプがあります。
たとえば、経営者に万が一のことがあったときの保障や、退職金準備を兼ねた長期積立など。
保険を活用することで、「保障・貯蓄・節税」の3つを同時に叶えられる場合もあります。
ただし、税制改正で取り扱いが変わることがあるため、契約時には必ず税理士等の専門家に確認を。
⑥福利厚生費の充実
福利厚生費とは、社員に対して行う「働きやすさをサポートする支出」です。
社員旅行・健康診断・慶弔見舞金・食事補助などが該当します。
正しくルールを守れば、全額を経費として処理できるケースも多く、社員の満足度向上にもつながります。
「節税とモチベーションアップの両立」ができるおすすめの方法です。
⑦決算賞与の活用
「決算直前に利益が出すぎている…!」というときに役立つのが、決算賞与です。
条件(支給額の事前決定・1か月以内の支払いなど)を満たせば、当期の損金に算入できます。
社員に喜ばれつつ、税負担も軽くできる一石二鳥の節税方法です。
⑧貸倒引当金の設定
将来、売掛金が回収できなくなるリスクに備えて、あらかじめ「貸倒引当金」を経費計上しておくことができます。
これは、取引先リスクのある中小企業にとって有効な保険のような制度。
税金を減らしながら、実際の経営リスクにも備えられるのがポイントです。
⑨固定資産の耐用年数・減価償却方法の見直し
設備や建物、車両などは、年数に応じて少しずつ経費化していきます(=減価償却)。
この「償却方法」を見直すだけで、節税のタイミングを調整できるんです。
減価償却には、主に「定率法」「定額法」の2つの方法があります。
ざっくりと表にしてみましたのでご参考になさってください。
| 法 法 | 経費のパターン | こんな会社に向いている |
|---|---|---|
| 定額法 | 毎年一定額 | 安定的に利益が出る会社、会計処理をシンプルにしたい会社 |
| 定率法 | 初年度に多く、徐々に減る | 利益が大きい年に節税したい会社、設備投資が多い会社 |
定額法は、毎年同じ額を経費にして安定させたいとき、定率法は初年度にまとめて経費を計上して節税したいときに利用することが多いです。
経営の状況や利益の見込みに合わせて使い分けるのがポイントです。
必要に応じて税理士に相談すれば、会社に最適な方法を提案してもらえますよ。
⑩少額減価償却資産の特例利用
中小企業は、30万円未満の資産を一括で経費処理できます(上限300万円まで)。
たとえばパソコンやオフィスチェア、プリンターなど。
この特例を使えば、設備投資をしても即座に経費にでき、節税しつつ事業効率もアップします。
⑪交際費の上限を把握して有効活用
中小企業の場合、年間800万円までは90%を損金算入できます。
得意先との会食や贈答品などが該当しますが、内容や金額をきちんと管理しておくことが大切です。
「全額ムダ」と誤解している経営者さんも多いので、正しく理解して活用しましょう。
⑫在庫の適正管理
決算時に在庫が多いと、その分だけ「利益が増えた」とみなされて税金が高くなります。
だからこそ、期末に過剰在庫を抱えないようにすることが、シンプルですが重要な節税です。
棚卸しを丁寧に行い、実際に不要な在庫は処分しておきましょう。
⑬クラウド会計を活用した経費管理の徹底
クラウド会計を使えば、経費の漏れを防ぎ、リアルタイムで利益を確認できます。
結果として、決算直前に「思ったより利益が出ていた!」という事態を防ぐことができます。
税理士との情報共有もスムーズになるため、節税相談もスピーディに進みます。
⑭青色申告特別控除を活かす(法人化前の個人事業主向け)
個人事業主から法人化を考えている方は、「青色申告特別控除(最大65万円)」のタイミングにも注目しましょう。
法人化の時期をずらすことで、この控除を最大限に活かせる場合があります。
法人化=すぐ有利とは限らないため、税理士に時期の相談をしておくと安心です。
関連記事:個人事業主と法人の違いは?どっちがお得?費用や判断のポイント
⑮資金繰り・投資計画と連動した節税設計
節税の本当の目的は、「税金を減らすこと」ではなく「お金を残して会社を強くすること」です。
だからこそ、単発的な節税ではなく、将来の設備投資や人材採用、退職金準備と連動させて計画を立てることが大切です。
「どのくらいの利益を残したいか」「来期どんな投資を予定しているか」など、長期的な視点で節税を設計するのが理想です。
\無料相談実施中です☺/
やってはいけない節税対策とは?
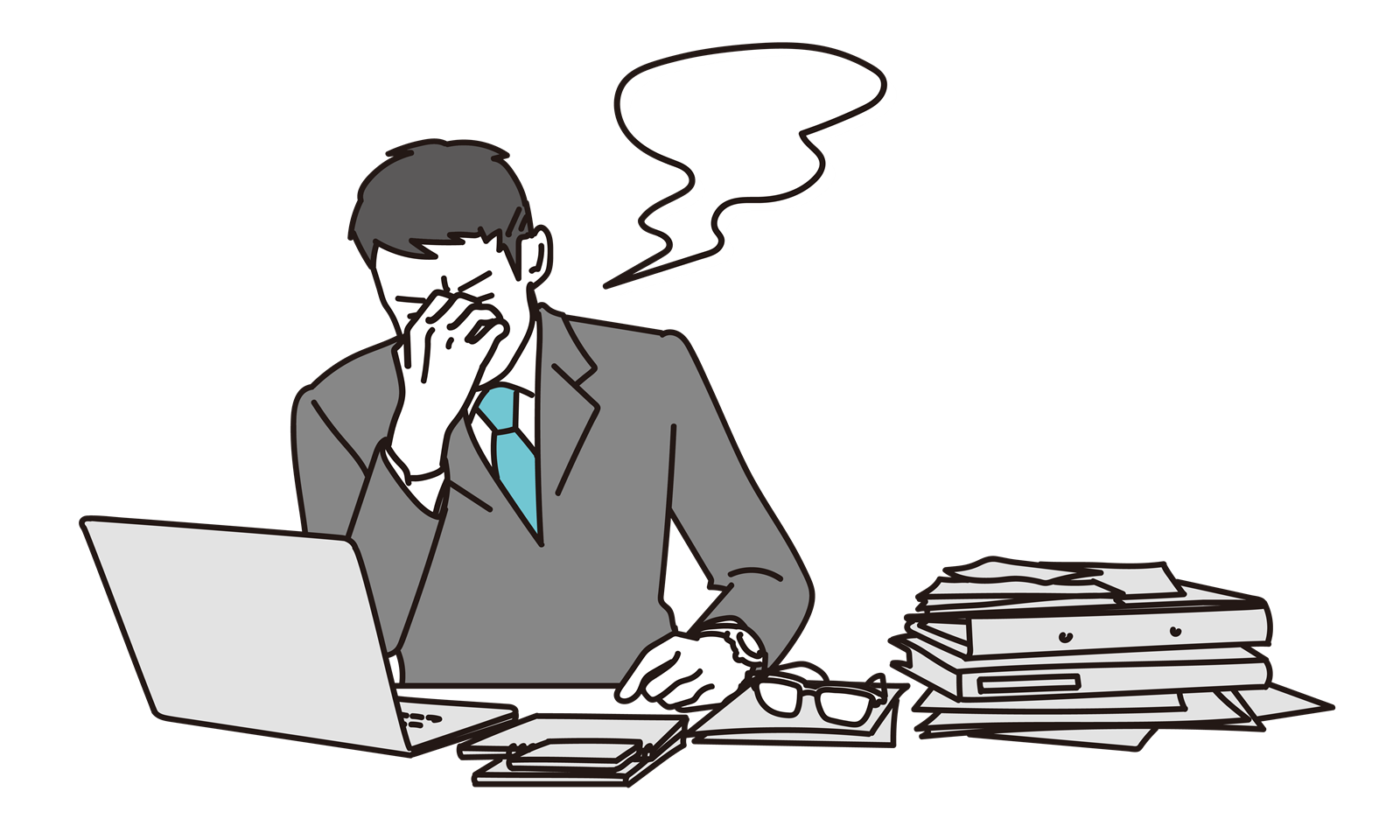
節税は会社の資金を守るための大切な手段ですが、間違った方法を取ると、思わぬリスクやトラブルを招くことがあります。
ここでは特に注意すべき「やってはいけない節税」を具体的にご紹介していきます。
架空経費や架空取引を計上する
一番危険なのは、実際には存在しない社員や取引先に給与や外注費を支払ったことにするような架空経費や架空取引です。
表面上は経費として処理されても、税務署が調査を行えばすぐに発覚します。
こうした行為は脱税と見なされ、追徴課税や罰金の対象となるだけでなく、最悪の場合は刑事責任に発展することもあります。
節税の目的であっても、実際に支出したもの以外を経費にすることは絶対に避けましょう。
個人の支出を会社経費にする
会社の資金と個人の資金を混同することも大きな落とし穴です。
たとえば、プライベート旅行や個人的な買い物を会社の経費として計上すると、税務署から指摘されるリスクがあります。
会社経費は、あくまで事業に必要な支出のみを対象とし、プライベートとの区別を明確にすることが基本です。
帳簿管理や領収書の整理をしっかり行うだけでも、節税トラブルを大きく減らせます。
保険を使った過剰な節税
法人契約の生命保険や損害保険には節税効果がありますが、節税目的だけで契約を増やしすぎるのは危険です。
保険料が重くなり、会社のキャッシュフローを圧迫してしまうことがあります。
保険は、将来の保障や資金計画とセットで活用することが重要で、節税効果だけを追求するのは避けましょう。
無理な仕入れや在庫増で利益を調整する
決算期に利益を減らすためだけに、不要な在庫を大量に仕入れるのも危険です。
現金が余計に減るうえ、在庫の管理負担も増えます。
節税はあくまで、会社の成長や資金繰りに支障がない範囲で行うことが大切です。
利益圧縮のために無理な仕入れや在庫増を行うと、逆に経営リスクを高めることになります。
節税を優先して事業投資を削る
利益を減らすことだけに意識を向けすぎると、必要な設備投資や人材採用を後回しにしてしまうことがあります。
短期的には税負担が減りますが、長期的には会社の成長機会を逃すことになりかねません。
節税は、事業投資や将来の成長とバランスを取った上で行うことが成功の鍵です。
税制改正を無視する
税制は毎年少しずつ変更されます。
過去の情報や古い節税ノウハウだけに頼っていると、思わぬトラブルに発展することがあります。
最新の税制情報を常に確認し、必要に応じて税理士に相談することが、正しい節税を実現するうえで欠かせません。
やってはいけない節税対策は、単に違法行為だけでなく、資金繰りや事業成長に悪影響を与えるものも含まれます。
節税の本質は「会社の資金を守りながら成長に活かすこと」です。
決して「脱税」にならないよう注意が必要です。
合法の範囲内で、無理のない計画を立てて取り組むことが、最も安全で効果的な節税です🌷
\無料相談実施中です☺/
節税対策を成功させるコツ

節税対策は、ただ「経費を増やす」「利益を減らす」だけではうまくいきません。
大切なのは、会社の成長や資金繰りとバランスを取りながら、無理なく実践することです。
ここでは、節税を成功させるためのポイントをわかりやすく解説します。
会社の利益や資金状況を把握する
まずは自社の現状を正しく把握することが基本です。
利益がどのくらい出ているのか、手元資金がどれくらい残っているのかを明確にしておくことで、節税策の効果やリスクを正確に見極められます。
利益を減らすために無理な支出をして、資金繰りが苦しくなる…という失敗はよくあるケースです。
「数字を見える化する」ことが、節税成功の第一歩です。
節税と成長戦略をセットで考える
節税は、単なる税金対策ではなく、会社の成長を支えるための手段でもあります。
例えば、設備投資や人材採用に資金を使うことで会社の生産性や売上が増えれば、将来的には節税以上のリターンが期待できます。
節税だけに意識を向けず、投資や福利厚生などの経営判断と組み合わせることが重要です。
複数の節税方法を組み合わせる
単独の節税策だけでは十分な効果が得られない場合もあります。
役員報酬の調整、退職金制度、経営セーフティ共済、福利厚生の充実など、複数の方法を組み合わせることで、無理なく、かつ効果的に税負担を軽減できます。
ただし、組み合わせ方によっては逆にキャッシュフローを圧迫する場合もあるため、計画的に行うことが大切です。
節税策は早めに計画する
節税は「決算直前に思いついて実行するもの」ではありません。
特に設備投資や退職金、賞与などの節税策は、年度初めから計画しておくことで最大限の効果を発揮します。
計画的に準備することで、無理のない支出で節税でき、資金繰りも安定します。
税理士などの専門家に相談する
節税は法律の範囲内で行う必要がありますが、制度は年々変化し、さらに複雑化していきますよね。
「この経費は認められるのか」「どの方法が会社に合っているか」を自己判断で行うと、リスクが高くなります。税理士に相談すれば、自社に最適な節税策の提案や、将来を見据えた資金計画のアドバイスを受けられるので安心です。
節税対策を成功させるには、会社の現状を正しく把握すること、成長戦略とセットで考えること、複数の方法を組み合わせること、早めに計画すること、そして専門家に相談することがポイントです。
この5つを意識するだけで、無理なく安全に節税を実現し、会社の将来に向けた資金をしっかり残すことができます。
関連記事:税金は誰に相談したらいい?税理士を活用する方法と注意点
\無料相談実施中です☺/
まとめ
法人の節税対策は、会社の資金を守りつつ、成長のために賢くお金を使うための大切な手段です。
今回ご紹介したように、役員報酬の調整や退職金制度、共済制度の活用、福利厚生の充実など、さまざまな方法があります。
しかし、自己流で行うと、思わぬトラブルや資金繰りの悪化を招くこともあるため注意が必要です。
節税を成功させるコツは、会社の利益や資金状況を把握したうえで、成長戦略とセットで計画的に実施することです。
そして、法律の範囲内で安全に行うために、税理士などの専門家と相談しながら進めることが最も確実な方法と言えます。
「どの節税策が自社に最適なのか」「効果的に税負担を減らしたいけどリスクも不安…」と悩むときは専門家に相談すると安心です。
私たち税理士法人ストラテジーでは、会社の状況に合わせた節税策の提案や、将来の資金計画まで一緒に考えるサポートを行っています。
気軽に相談できる無料相談も用意していますので、まずは状況を整理しながら、最適な節税プランを一緒に考えてみませんか?
ぜひ以下のボタンよりお申込みをお待ちしております✨
\無料でご相談いただけますのでお気軽にご連絡ください☺/