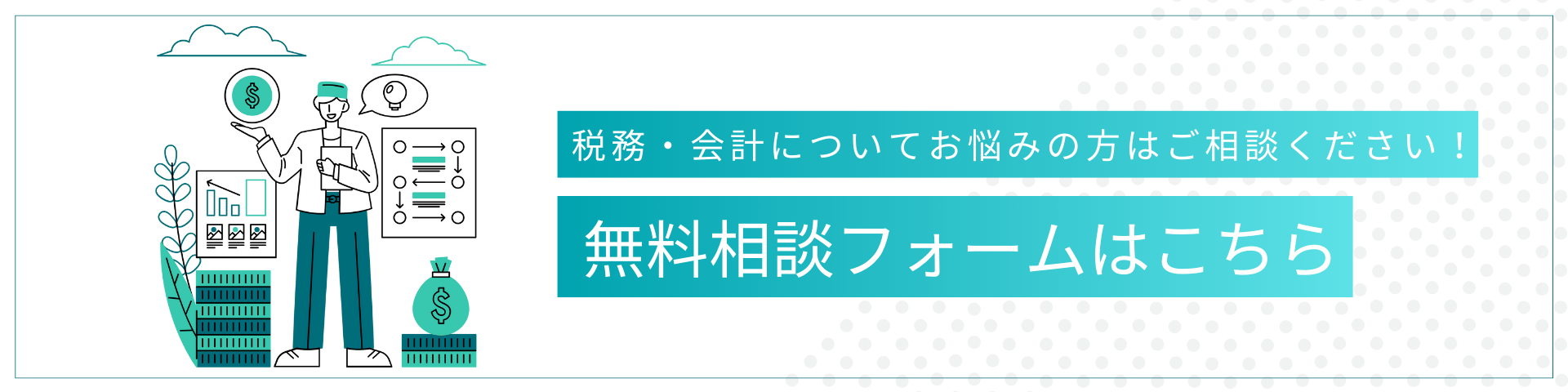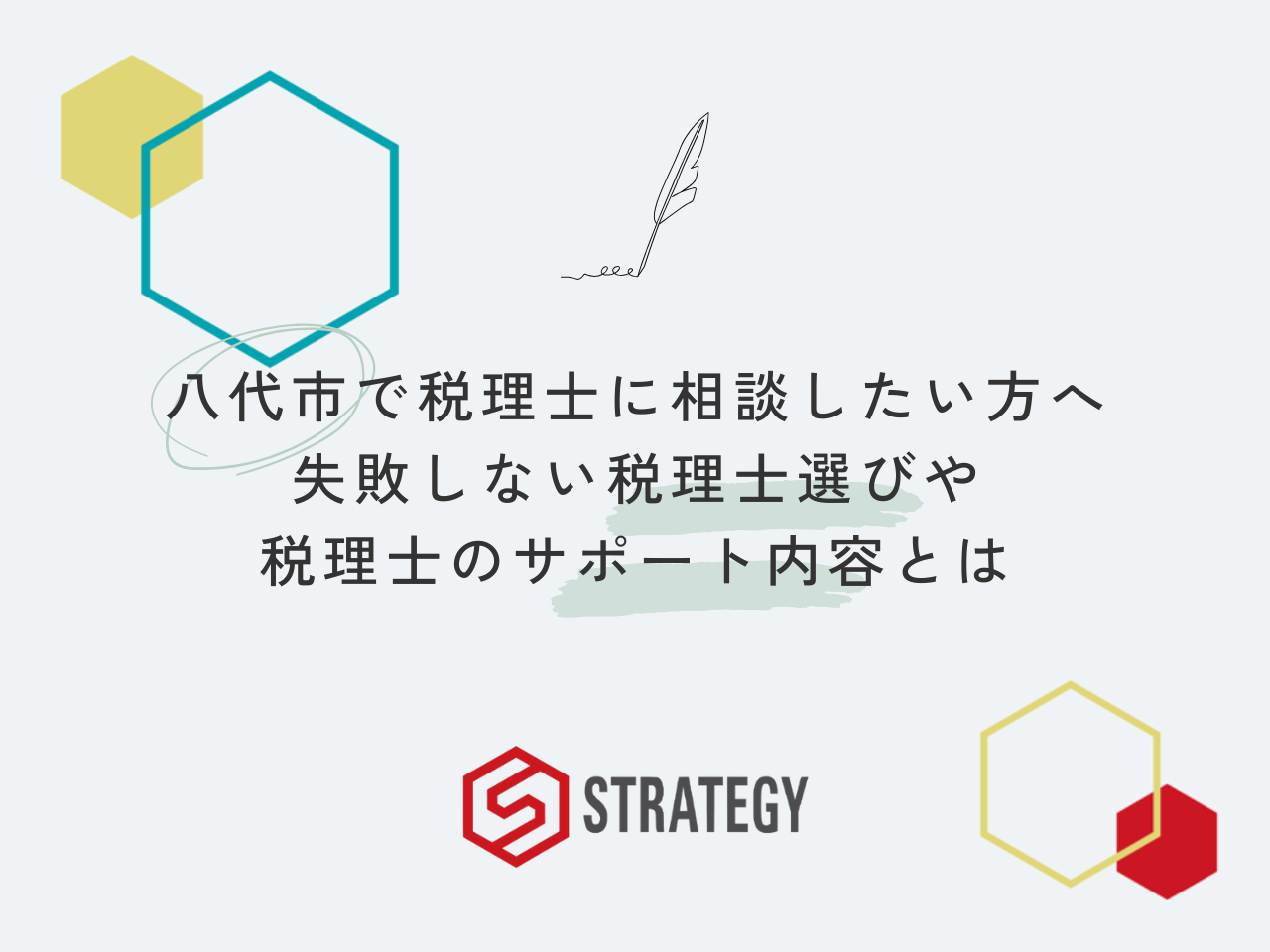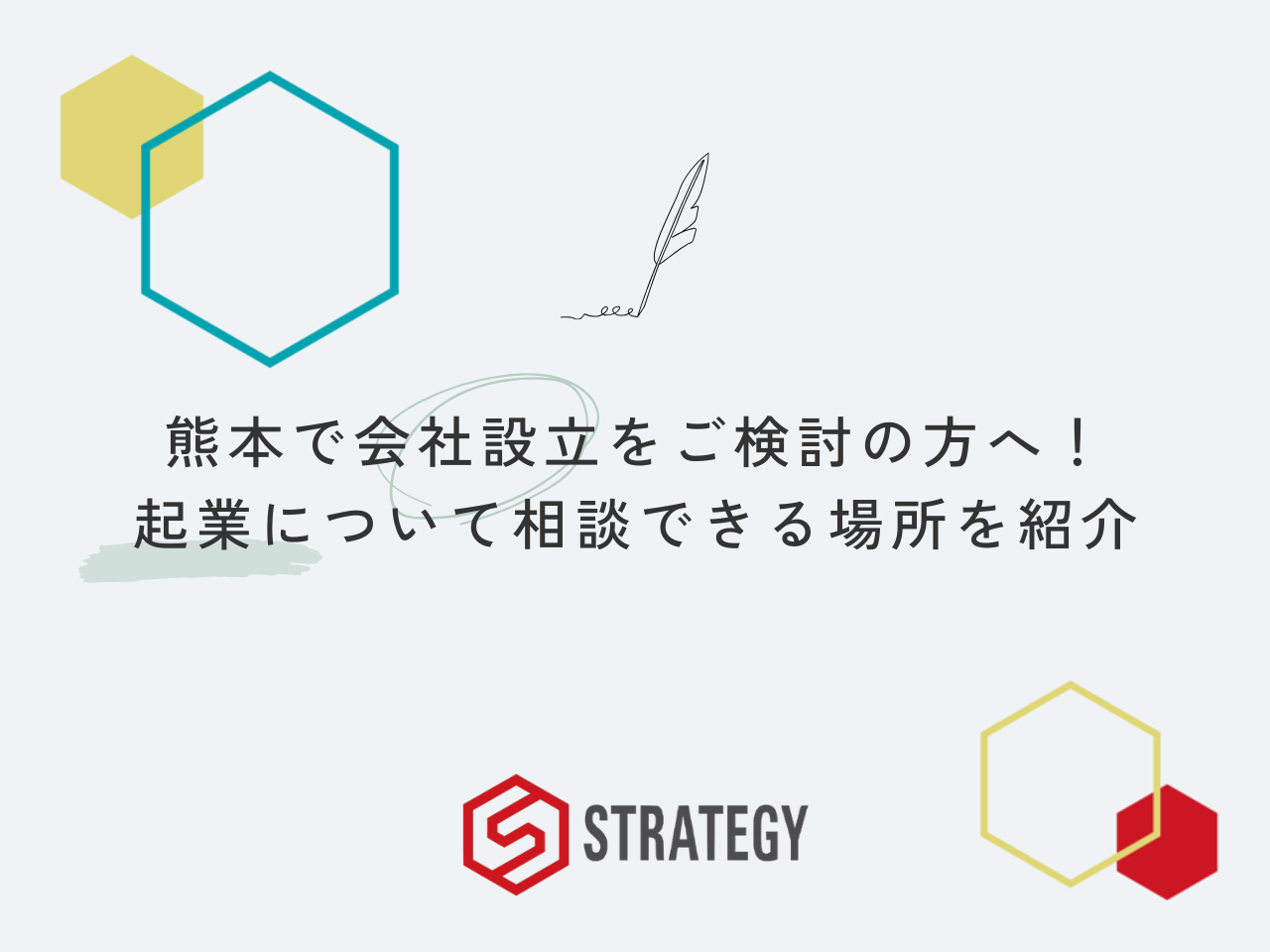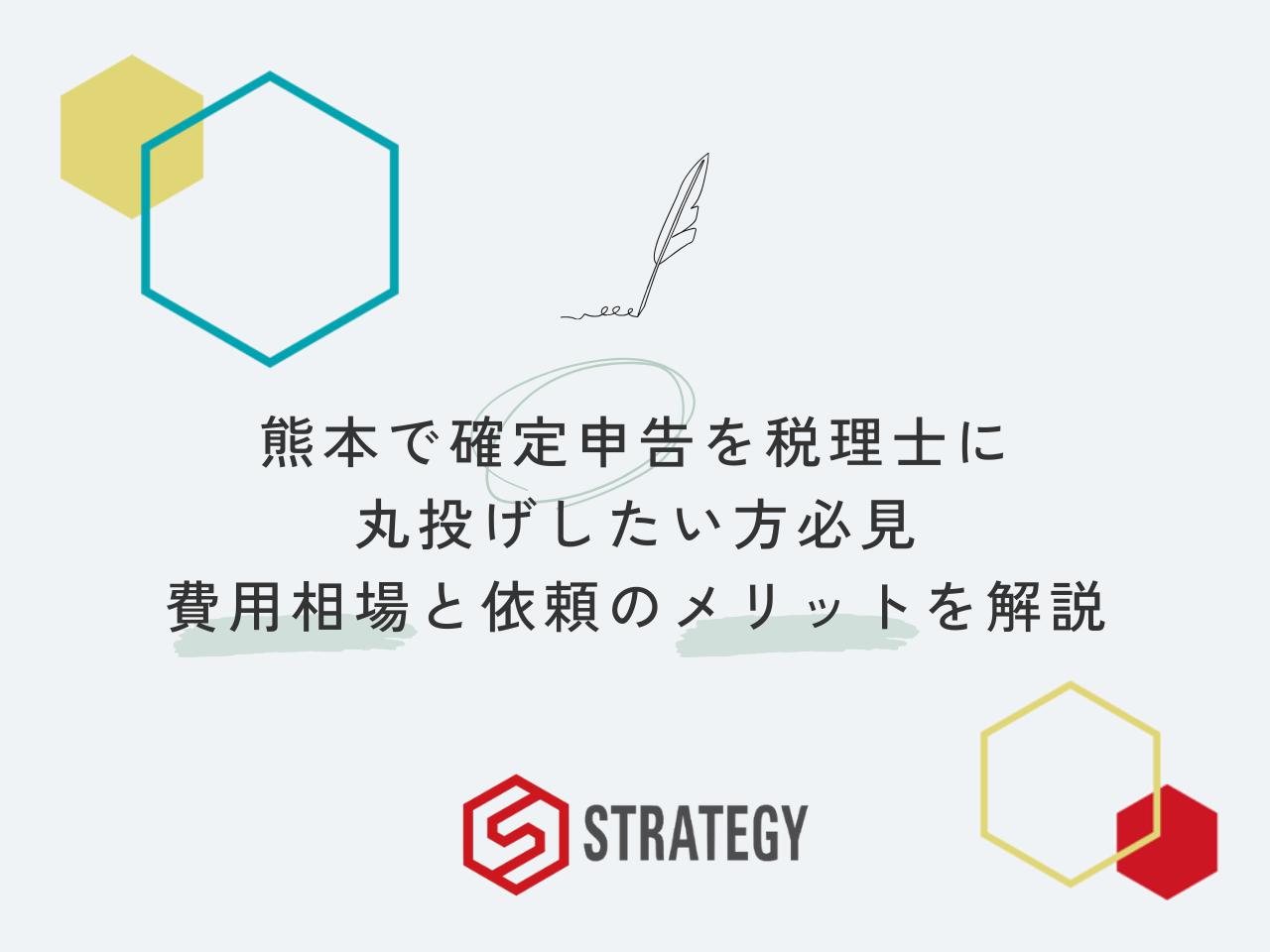相続で申告が不要なケースとは?判断基準と注意点を税理士が解説
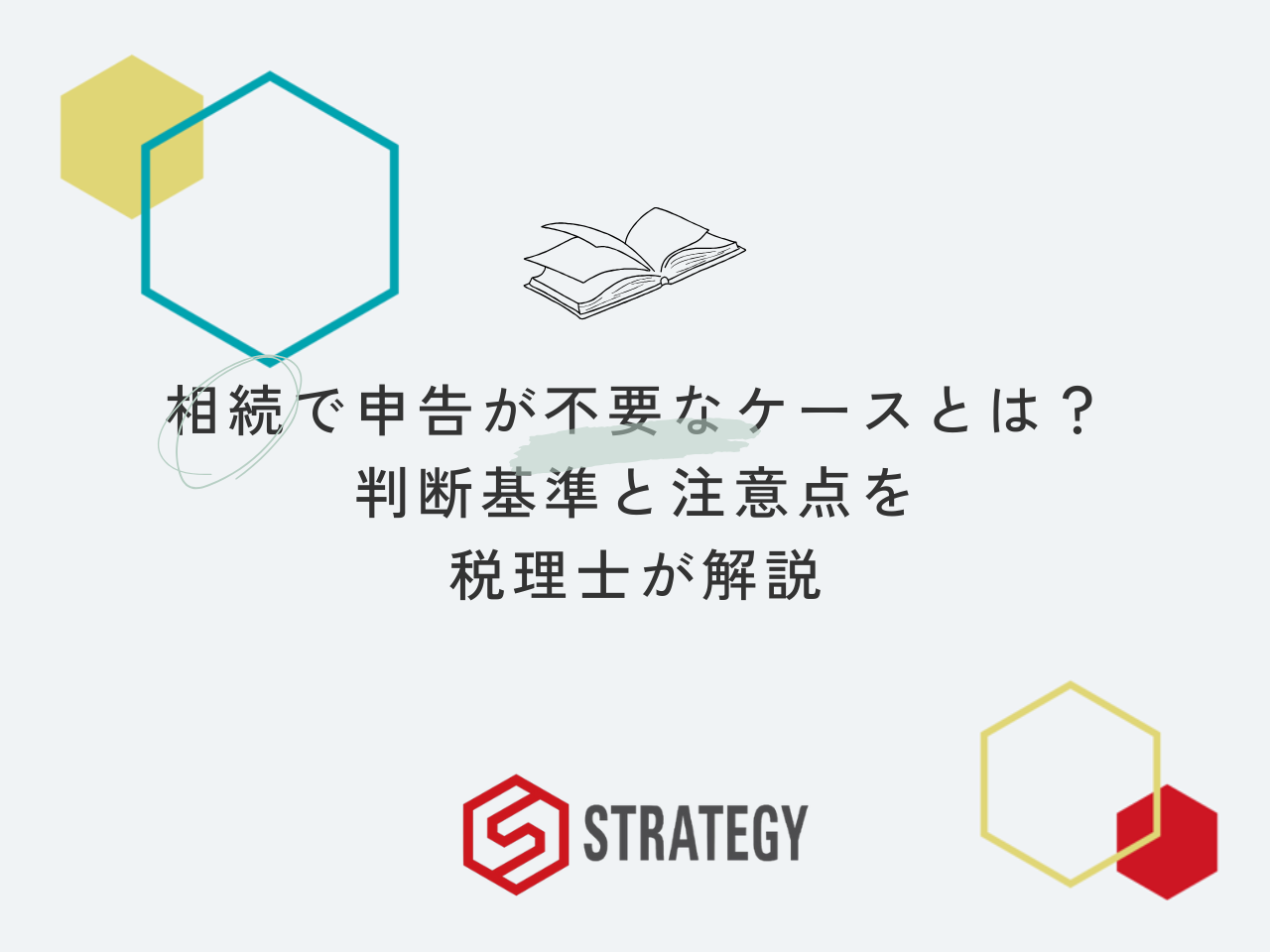
「相続が発生したけれど、うちは相続税の申告って必要なのかな……?」
身近な方を亡くされたばかりで、まだ気持ちの整理もつかない中、役所や金融機関から届く書類に戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
とくに「相続税の申告が必要かどうか」については、ケースによって大きく異なります。
実は、すべての相続で申告が必要というわけではありません。
一定の条件に当てはまれば、「申告不要」となることもあるのです。
しかし一方で、「うちは大丈夫だろう」と自己判断してしまったばかりに、あとから税務署から指摘を受けてしまうケースも少なくありません。
見落としや誤解がトラブルのもとになるような、そんなデリケートなテーマだからこそ、正しい知識をもって判断することがとても大切です。
この記事では、「相続税の申告が不要になるケース」について、税理士の視点から解説していきます。
申告の要・不要を判断する基準や注意点、さらに申告が不要でもやっておきたい手続きについてもご紹介していきます。
「申告不要って聞いたけど、本当に大丈夫?」と少しでも不安に思っている方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
1.相続税の申告が「不要」となるケースとは?
1.1.基礎控除以下
1.2.非課税財産が多い
1.3.配偶者の税額軽減の適用
2.申告が不要かどうかを「自己判断」するリスク
2.1.見落としや評価ミスが多い相続財産とは
2.2.後から税務署に指摘されるとどうなる?
3.相続税の申告が不要でも「やっておいた方がいい」こと
3.1.遺産分割協議書の作成
3.2.名義変更や登記手続きもお早めに
3.2.税理士への相談で「安心」を得られる
4.相続税の申告が必要になるケースのチェックリスト☑
4.1.要申告の主な条件
4.2.こんな場合は注意!実例で見る申告義務の見落とし
4.3.要・不要の判断に迷ったら【無料チェックサービス】の活用を
5.よくあるご質問(FAQ)
5.1.Q1. 相続人が1人だけの場合でも申告は不要ですか?
5.2.Q2. 生命保険金があるのですが、申告は必要ですか?
5.3.Q3. 相続人どうしで話し合い中ですが、申告期限を過ぎても大丈夫ですか?
6.まとめ
相続税の申告が「不要」となるケースとは?
さっそく、どのような条件のもとで相続税の申告が不要となるのかをお伝えしていきます。
相続税というと、「誰かが亡くなったら必ず申告が必要」と思っている方も多いかもしれません。
ですが、実は相続税の申告が不要になるケースも少なくありません。
基礎控除以下
相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があります。
この金額以内であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
基礎控除の金額は、次の計算式で決まります。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円 までの相続財産であれば申告不要となります。
ただし、ここで注意したいのが「相続財産の評価方法」です。
預金や現金はわかりやすいですが、不動産や株式などは評価が複雑になりがちです。
「だいたいこのくらいだろう」と自己判断してしまうと、実際には基礎控除を超えていた…ということも起こり得ます。
非課税財産が多い
相続財産のなかには、そもそも課税対象とならないものもあります。
こうした「非課税財産」が多いケースでは、申告が不要となる可能性があります。
主な非課税財産には以下のようなものがあります。
- 【生命保険金】……相続人1人あたり500万円まで非課税
- 【死亡退職金】……生命保険と同様、1人あたり500万円まで非課税
- 【墓地・仏壇・仏具】……常識的な範囲であれば非課税対象
- 【公益事業に使われる財産】……国・地方公共団体・特定の公益法人等に寄付された財産など
たとえば、遺産の大部分が生命保険金で、人数分の非課税枠に収まっている場合などは、課税対象額がゼロとなるため、結果として申告が不要になることもあります。
配偶者の税額軽減の適用
相続人に配偶者がいる場合、相続税が大幅に軽減される制度があります。
それが「配偶者の税額軽減」です。
この制度を適用すると、以下のどちらか多い方の金額までは相続税がかかりません。
- 配偶者の法定相続分
- 1億6,000万円まで
このため、財産の多くを配偶者が相続する場合、結果的に税額がゼロとなり、申告が不要になるケースもあるのです。
ただし、ここには大きな落とし穴があります。
実はこの「配偶者の税額軽減」を使うには、申告が必要なことがほとんどなのです。
申告をしないと軽減措置が適用されず、あとから税額が発生する可能性も。
つまり、「配偶者がほとんど相続したから申告しなくていいだろう」と思っていたら、
逆に申告が必要なパターンだったということもよくあります。
申告が不要かどうかを「自己判断」するリスク
「財産そんなにないし、たぶん申告は不要でしょ」
そう思って手続きをしないまま放置してしまう方が、実はとても多いです。
しかし、「自己判断」ほど、相続では危険なことはありません。
申告が不要だと思い込んでいたのに、あとから税務署に指摘されて、
結果として追徴課税や延滞税が発生してしまった…!というご相談は、税理士のもとに日々寄せられています。
ここでは、そのようなリスクが生まれてしまう背景について解説していきます。
見落としや評価ミスが多い相続財産とは
相続財産の中には、見た目の金額だけでは判断できないものがあります。
特に注意が必要なのが以下のようなケースです。
- 不動産の評価額(固定資産税評価額ではなく、相続税評価額を使う)
- 未上場株式や持ち株(評価が複雑で専門性が必要)
- 名義預金(親の口座に子の名義が使われていたケースなど)
たとえば「父の名義だけど、実質的には私の預金だから相続財産ではない」と判断してしまうと、
税務署から「それも相続財産です」と否認されてしまうこともあります。
つまり、表面だけを見ての判断では、本当の評価額が見えてこないというのが相続の怖さです。
専門家の視点から精査しなければ、思わぬ見落としをしてしまうリスクがあります。
後から税務署に指摘されるとどうなる?
「申告が不要だと思っていたのに、税務署からおたずね文書が届いた…」
こんなケースも実際によくあります。
税務署は、被相続人の預貯金や不動産の保有状況など、かなりの情報を事前に把握しています。
そのため、「申告がされていないのに、この金額はおかしい」と感じた場合、調査の対象になります。
万が一、申告漏れがあった場合には…
- 過少申告加算税(10〜20%)
- 無申告加算税(15〜20%)
- 延滞税(納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年14.6%)
といったペナルティが課される可能性があります。
特に「無申告」の場合、悪質と見なされやすいため、加算税の率も高くなります。
こうした税負担に加えて、精神的にも大きなストレスを抱えることになります。
せっかく相続した財産なのに、後悔のもとになってしまった…という声も多いのです。
相続税の申告が不要かどうかは、実際に詳細な財産内容を精査しないと判断できないケースがほとんどです。
少しでも「大丈夫かな?」と思ったら、自己判断せず、まずは専門家に相談することをおすすめします🍀
相続税の申告が不要でも「やっておいた方がいい」こと
「相続税の申告は不要だったから、手続きは何もいらないよね?」
そう思って何もせずにいると、将来思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
たとえ税務署への申告が不要だったとしても、相続に関する手続きはまだまだ終わりではありません。
ここでは、申告不要なケースでもやっておいた方が安心なことを3つご紹介します。
遺産分割協議書の作成
まず取り組んでおきたいのが、「遺産分割協議書」の作成です。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その合意内容を記載した書類です。
主に遺言書がない場合や、遺言で指定されていない財産がある場合に作成されます。
相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するのかをしっかり決めて書面に残す必要があります。
- 協議書がないと、不動産の名義変更や預金の解約ができない
- 口約束やメモだけでは後々トラブルのもとに
- 相続人全員の合意と実印、印鑑証明書が必要
相続トラブルは、相続税がかからない家庭でも多く発生しています。
「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていた家族ほど、のちのち揉めやすいもの…。
円満な関係を続けるためにも、協議書の作成はしっかり行いましょう。
名義変更や登記手続きもお早めに
申告が不要だからといって、不動産や預貯金の名義をそのままにしておくと、将来になって手続きが困難になることも。
例えば以下のようなことが起こり得ます。
- 不動産の名義変更をしないまま相続人が亡くなった → 手続きが複雑に
- 銀行口座が凍結されたまま放置 → 相続人全員の手続きが必要に
- 登記しないまま放置 → 相続登記の義務違反で過料(10万円以下)
令和6年(2024年)4月からは、不動産の相続登記が義務化されており、放置すると罰則が科される可能性もあります。
手続きを後回しにせず、「申告不要でも、名義変更は早めに」と覚えておきましょう!
税理士への相談で「安心」を得られる
相続税の申告が不要かどうか、自分たちだけで判断するのはとても難しいもの。
評価の難しい財産が含まれていたり、非課税枠の使い方を誤っていたりすると、「実は申告が必要だった…!」というケースもあります。
そこでおすすめしたいのが、税理士への無料相談です。
- 財産内容を整理しながら、申告の要否を専門的にチェック
- 不動産や預金の評価方法、名義の扱いも明確に
- 必要な手続き・不要なものの切り分けをプロが判断
税理士法人ストラテジーでは、初回無料でのご相談を受け付けています。
「申告しなくていいかどうか確信が持てない…」という方は、どうぞお気軽にご相談ください☺
関連記事:熊本で相続に強い税理士をお探しの方!相続税申告・対策のポイント
相続税の申告が必要になるケースのチェックリスト☑
「うちは申告しなくて大丈夫そう」と思っていても、
実は申告が必要だった…というケースは少なくありません。
特に相続税の対象になる財産は、評価額や扱い方によって大きく変わるため、見た目の金額だけで判断するのは危険です。
ここでは、相続税の申告が必要になる代表的な条件や、
見落としがちなポイントについてチェックリスト形式で解説していきましょう。
要申告の主な条件
相続税の申告が必要になるかどうかのポイントは、課税対象となる財産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかです。
以下のようなケースに当てはまる場合は、申告が必要になる可能性が高くなります。
✔️ 被相続人の財産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円×相続人の数)を超えている
✔️ 複数の不動産や投資資産を所有していた
✔️ 生命保険金や死亡退職金が、非課税枠(500万円×法定相続人)を超えている
✔️生前贈与を頻繁に受けていた(相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算)
✔️配偶者の税額軽減を使う予定(※この特例を使うには申告が必要です)
どれかひとつでも当てはまる場合は、「申告が必要かも?」と考えるべきラインです。
こんな場合は注意!実例で見る申告義務の見落とし
以下のようなケースでは、「申告が不要だと思っていたけれど、実は必要だった」ということがよくあります。
💡実例1:親名義の預金に手を付けていた
「父の通帳だったけど、家族の生活費用だったから…」と引き出していたお金。
税務署は、名義と管理状況を確認したうえで、「名義預金」=相続財産と判断することがあります。
💡実例2:生前贈与が多かった
毎年110万円ずつ贈与していた場合でも、形式が不十分だと相続財産に加算されるケースがあります。
特に、贈与契約書がなかったり、通帳が親の管理下にあった場合は要注意です。
💡実例3:不動産評価の誤解
固定資産税評価額をそのまま使って「基礎控除内だ」と判断してしまうケースも…。
相続税評価では「路線価」や「倍率方式」による専門的な計算が必要です。
こういった見落としが積み重なると、当初は基礎控除以下だったつもりが、実は大きくオーバーしていた…ということにもなりかねません。
要・不要の判断に迷ったら【無料チェックサービス】の活用を
相続税の申告が必要かどうかは、財産の種類や構成、家族構成によって本当に様々です。
「これって課税対象?」「この評価額で合ってる?」と少しでも不安を感じたら、プロにチェックしてもらうのが一番確実です。
税理士法人ストラテジーでは、
- 相続税の申告が必要かどうかの判断チェック
- 相続財産の簡易評価
- 非課税枠や特例の活用可能性の確認
などを含めた、初回無料相談を承っております。
「大丈夫だと思うけど、念のため…」という段階でのご相談も歓迎です☺
相続の不安やモヤモヤを、まずはお気軽にご相談くださいね。
よくあるご質問(FAQ)
ここでは、実際に相続が発生した方からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
「これ、うちの場合はどうなるのかな?」と不安に思われた方は、ぜひご参考にされてください。
Q1. 相続人が1人だけの場合でも申告は不要ですか?
A1. 財産の総額が基礎控除内であれば、相続人が1人でも申告は不要です。
基礎控除は、「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算されます。
たとえば相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円です。
つまり、相続財産の評価額が3,600万円を超えていなければ、申告は必要ありません。
ただし、不動産や名義預金など評価の難しい財産がある場合は、一度専門家に見てもらうことをおすすめします。
Q2. 生命保険金があるのですが、申告は必要ですか?
A2. 非課税枠の範囲内であれば、申告は不要になることがあります。
生命保険金は、「500万円×法定相続人の人数」までは非課税となります。
たとえば相続人が2人であれば、1,000万円までが非課税です。
ただし、それを超える金額は相続財産に加算されるため、他の財産と合わせて基礎控除を超えるかどうかで、申告が必要になるかどうかが決まります。
また、契約者や受取人の関係によっては、贈与税の対象となるケースもあるので要注意です。
Q3. 相続人どうしで話し合い中ですが、申告期限を過ぎても大丈夫ですか?
A3. 原則として、相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」です。
たとえ遺産分割協議がまとまっていなくても、一旦申告を行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」などを提出する必要があります。
そのまま期限を過ぎてしまうと…
- 各種特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例など)が使えなくなる
- 無申告加算税・延滞税が発生する可能性がある
というデメリットが生じます。
つまり、話し合いがまとまっていなくても、期限までに対応することが大切なんです。
まとめ
相続税の申告について、「うちは関係ないかな?」と思っていた方も、
ここまで読んでくださったことで、判断の難しさや注意点を実感されたのではないでしょうか。
たしかに、基礎控除内におさまる財産であれば、相続税の申告は不要となるケースもあります。
しかし、「申告がいらないかどうか」こそ、正確な判断が求められる分野なのです。
- 不動産や預金の評価方法を間違えていないか
- 名義が複雑な財産や、見落としがちな贈与がないか
- 非課税枠の使い方や特例の適用ミスがないか
こうした点を専門家と一緒に確認することで、
「本当にうちは大丈夫だった」と心から安心することができます!
申告不要であっても、遺産分割や名義変更などの手続きは残っていますし、
のちのちのトラブルを避けるためにも、今のうちに正しい情報と向き合うことが大切です。
こちらのWEBサイトでも、相続に関する情報を掲載しておりますので、ご興味のある方はご覧になってみてください!
\無料でご相談いただけますのでお気軽にご連絡ください☺/