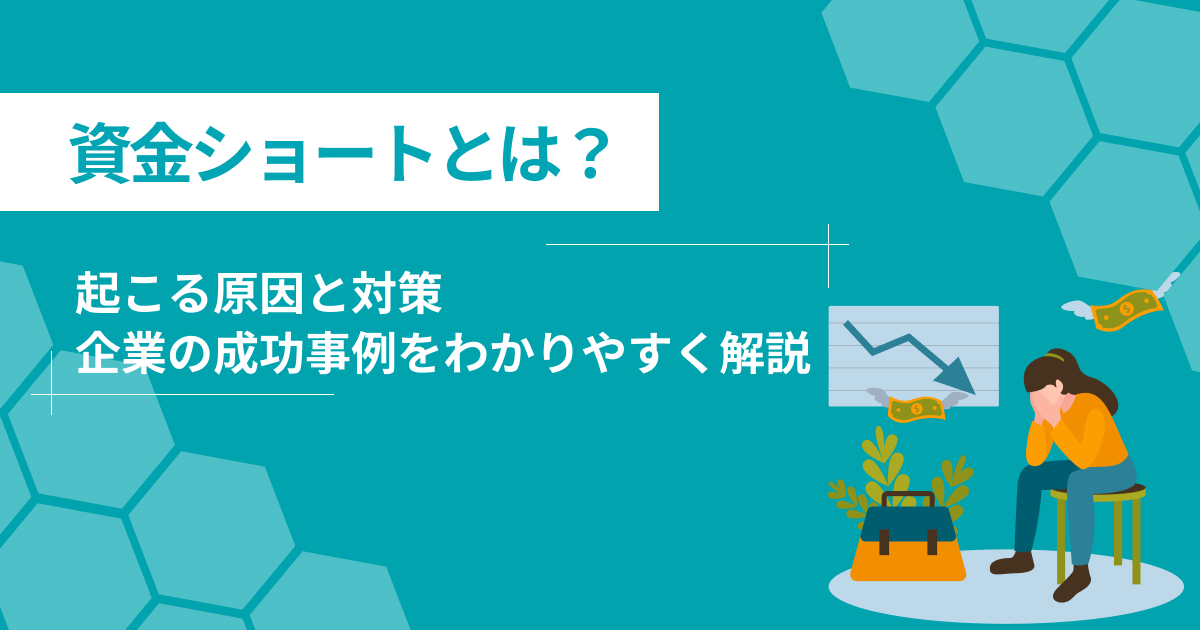資金繰りの安定は会社経営において非常に重要なポイントであり、収支のバランスが崩れ資金が不足してしまうと「資金ショート」と呼ばれる状況に陥ってしまい、状況によっては会社の存続そのものが難しくなりかねません。
しかし今現在でも資金繰りに苦労している企業は決して少なくはなく、たとえ売り上げが伸びている状況であっても資金ショートに陥るリスクは存在しています。
この記事では、資金ショートという言葉の正しい意味合いから、手元の資金が不足したことで発生しかねない会社経営への影響などもご紹介します。
さらに資金ショートに陥った場合の対処法や、そうならないための対策なども解説させていただきますので、資金繰りの安定した会社経営を目指す経営者様は、ぜひこの記事を最後までお読みください。
資金ショートとは資金不足で経営が止まる危険な状態
手元にある現金が不足し、仕入れに関する費用や公共料金など、会社経営において必要な支払いが実行不可能となってしまった状況を指すのが「資金ショート」という言葉であり、不渡りを出す原因などにもなるだけでなく、会社経営を止めてしまう直接的な要因ともなり得る非常に危険な状態です。
資金ショートを債務超過と混同されている方も少なくはありませんが、実際にはこの2つの言葉は大きく異なる状況を指しており、対処方法や対策も大きく異なるため注意が必要です。
また「資金ショート=倒産」ではないものの、状況を放置しておけば倒産に直結してしまう可能性は高く、さらにどうにか資金ショートの状況を改善できたとしても、企業として大きなダメージを負ってしまうことになりかねません。
資金ショートへの対策などを学ぶ前に、まずは資金ショートに対して正しい知識を持ち、陥った際にはどのような影響が予想されるのかを知っておいていただくことが大切です。
債務超過との違いを理解して混同を防ぐ
「債務超過」は資金ショートと同じ、または似た表現として混同されやすい言葉の1つです。
しかし債務超過は企業が保有する資産額よりも負債額が上回っている状態を指しており、支払いに利用できる資金の有無とは直接的な関係はありません。
債務超過が続いた場合には、返済リスクの高さなどを考慮され金融機関からの融資が受けにくくなるなどのデメリットが考えられますが、手元に資金が残っていれば取引先への支払いなどは実行可能であるため、支払いが不可能となる資金ショートは債務超過よりも一層危険な状況と考えられます。
また「赤字」も資金ショートと近い意味合いを持つと勘違いされやすい言葉ではありますが、赤字は一定期間内の収入を支出が上回っている状況となり、赤字の場合も債務超過と同様に手元にある資金が不足していると限定されてはいないという大きな違いがあります。
- 資金ショート・・・手元の資金が支払いに必要な額に対して不足している状態。取引先などへの支払い不可
- 債務超過・・・資産額を負債額が上回っている状態。手元に資金があれば取引先などへの支払いは可能
- 赤字・・・支出が収入を上回っている状態。手元に資金があれば取引先などへの支払いは可能
資金ショート・債務超過・赤字を簡単に説明させていただくと、上記のリストのようになります。
この中でも会社経営において最も危機的な状況となるのは、取引先への支払いが不可能となる資金ショートで間違いなく、資金ショートは企業として対処対策を行う優先度が高いという根拠にもなります。
資金ショートと不渡りの関係性を解説
企業間の取引における「不渡り」とは、小切手や約束手形を支払期日になっても決済できない状態を指し、「不渡りを出す」のように使われます。
- 0号不渡り—振出人が原因ではない、受取人の都合や手形や小切手発行時の不備などによる不渡り
- 1号不渡り—資金不足や当座預金口座の解約など、振出人が原因となる不渡り
- 2号不渡り—0号または1号に該当しない不渡り。手形の盗難など
不渡りには上記の3つの種類がありますが、一般的に言われている不渡りとは1号不渡りを指しています。
取引先や金融機関に対して不渡りを出してしまうと、企業としての信用を大きく損なうことになり、取引先との関係が悪化した場合には取引の停止の危惧があり、金融機関が相手となった場合には融資を受けられなくなるなど、大きなデメリットに繋がる危険があります。
また資金ショートは不渡りに直結している状態ではありますが、不渡りを出さざるを得ない状態であっても必ずしも手元資金が不足しているとは言い切れないため同じ意味とはならず、混同しないよう少しご注意ください。
資金ショートが起きると信用低下や取引停止の恐れ
不渡りの大きな要因ともなる資金ショートは、順調であったはずの会社経営を途端に停滞させ、倒産という危険まで大幅に高めてしまいかねません。手元の資金が不足した状況では、取引先への支払いが実行できず、さらに従業員への給与未払いや材料不足などにも繋がっていくことが考えられます。
そして資金ショートは企業にとって何よりも大切な「信用」にも、大きな悪影響を与えかねないのです。失った信用を取り戻すのには多大な時間と労力を消費し、事業拡大など会社を育てていく道も厳しくなっていきます。
どのような影響を資金ショートが起こす可能性があるかを知っていただくことも、資金ショートに陥る危険を減らすのに必要なポイントとなります。
支払い遅延によって取引先からの信用が下がる
資金ショートの状態になってしまうと、取引先に対して買掛金を決済することもできず、取引先の資金繰りに大きな負担を押し付ける事にもなりかねません。
場合によっては取引先の経営にも多大な悪影響を与える危険もあり、自社だけでなく取引先企業までも倒産の危機に陥らせてしまうかもしれないのです。
またそこまでの被害にはならずに済んだとしても、支払いを遅延させてしまったことが取引先からの信用を下げる危険性は非常に高く、その後の取引額の引き下げや、最悪の場合には取引停止となる可能性も否定できません。
取引停止や与信の引下げは、売上額の減少や事業継続に必要な材料が確保できないという状況にも繋がりかねないため、資金ショートのピンチを乗り切れたとしても、その後の会社経営において大きな損失となってしまうことが予想されます。
給与の遅れが従業員の信頼を失う原因になる
支払いの対象は取引先だけでなく、給与を支払うべき自社の従業員もその対象となります。
従業員への給与未払いは、信頼を失うのはもちろんですが働く意欲そのものも低下させてしまう原因となり、サービス内容や作業スピードの低下などを引き起こすことが考えられます。
そして事業の質が低下してしまうと客離れや売上額の低下に繋がっていくのは自然の流れであり、資金繰りをさらに苦しくしてしまうという悪循環に陥る危険が高いのです。
また給与の未払いは従業員が退職を考えるのに十分な理由となることから、従業員不足によって事業の継続が不可能になるという危険も無視することはできません。
もちろん給与が支払えない状況になってしまう前の対策はもちろんですが、未払いになった際には今後の見通しの説明など丁寧な対応を行っていただくことが求められます。
黒字でも倒産の危険があり早期対策が必要になる
手元にある資金が不足するのは、経営が傾いている時だけではありません。
たとえば、売上げが伸びると予想し大量に発注を行った際には、売掛金を回収する前に材料費などの支払いを行うことになる可能性が高く、予想外の出費が重なってしまったり計画していた融資が受けられなかったりした場合には資金ショートに陥る危険が高まります。
また安定した売上げが続いている状況であっても、自然災害の影響などで一時的に売上げが減少してしまった場合には、多くの在庫を抱えたことで保管費などが通常より多めに発生してしまい、資金繰りを苦しくする原因となる可能性も否定できません。
その他にも今後の事業拡大を目指した大規模な設備投資を行った際にも、その後の資金調達のトラブルや予想していたよりも売上げが少なかった場合には、資金ショートへ繋がるかもしれません。
このように、安定した経営を行い黒字が続いている状態であっても、資金ショートを起こしてしまう危険は常に存在しています。
最悪の場合には、黒字でありながら経営が立ち行かなくなる「黒字倒産」となってしまう危険性もあることから、資金ショートに対しての早期対策は非常に重要となります。
銀行評価が下がり追加融資が難しくなるリスク
銀行など金融機関から融資を受けるには審査があり、経営状況が安定していない企業は審査通過が難しくなります。
金融機関にとっては貸倒れのリスク対策は当然のことであり、信用情報の低い企業が審査通過しにくいのは仕方のないことではありますが、資金繰りにとっては大きな問題となりかねません。
そして資金ショートとなってしまった企業は、どうしても金融機関から評価を下げられてしまう傾向があり、銀行などへ追加融資の申込を行ったとしても断られてしまったり、融資可能となった際にも高い金利や低い融資額など厳しい条件が提示されてしまう可能性が高くなります。
銀行や日本政策金融公庫などから融資を受けるには、数週間から数か月の期間を必要とすることも珍しくはありませんが、資金ショートに陥った後では融資を受けられる期待が大きく低下してしまいますので、可能な限り期間と手元資金に余裕がある状況での融資の申込みをご検討ください。
資金ショートの原因は入金遅れや管理不足で起こる
資金ショートへの対策を行うためには、資金ショートに陥る原因を知っておいていただくことも大切です。
手元に資金が潤沢にあれば資金ショートが起きにくくなるのは間違いありませんが、特に個人事業主や中小企業にとっては容易なことではなく、どうしてもその時々に合わせた素早い対応が求められます。
しかしこれからご紹介する、資金ショートに陥る要因として代表的な4項目の内、どれが自社と関係する可能性が高いかを判断していただくことで、対策方法も見つけやすくなるはずです。
もちろん今は起こりえる可能性の低い要因であっても、発生しないと決めつけるのは危険ですので、もしもの場合に備えて対策を考えておくのは決して無駄にはなりません。
それぞれ順に解説します。
売上減少や入金の遅れで現金が足りなくなる
資金ショートとは支払額に対しての現金不足であり、その大きな要因となるのが収入に関する問題です。
予想を大きく超える売上げの減少などはその代表的な原因であり、売上げが回復しない場合には経営方針の転換なども視野にいれる必要がありますが、短期間で経営状況が改善されない場合には資金ショートへの対策としての資金調達が急務となります。
他にも売掛先からの決済の遅れも、現金が不足してしまう大きな原因となります。
現在も多くの企業が取引に売掛金を活用する掛取引を採用していますが、支払サイトは30日~60日程度が一般的であり、入金されるまでの期間の資金繰りが会社経営における大きな問題となっています。
そして予定よりも取引先からの入金が遅れた場合には、現金が不足する危険が大きく高まります。
また何らかの理由により入金を遅らせてしまった取引先は、経営状況が悪化していることが予想されるため、取引先の倒産により債権回収が不可能となる危険も無視できなくなります。
売上げの減少とは異なり入金の遅れに対する対処は容易ではありませんが、1つの取引先に頼り過ぎないことでリスクを軽減することができます。
在庫や仕入れのバランス崩れで資金が減る
売上げの減少とも無関係ではありませんが、在庫を多く抱えてしまうと資産の現金化を停滞させてしまい、利益が得られない状態が続き手元の資金を減らす原因になってしまいます。
また過剰な在庫は保管費用などの維持費を増加させてしまい、売れ時が来ないまま保管期間が長引くと、商品を劣化させるなどして資産としての価値も失うことになりかねません。
仕入れに関しても同様であり、売上げに対して仕入費のバランスが崩れてしまうと、支払額が売上げを大きく上回ってしまう危険が高くなり、保有する資金の減少を加速させてしまいます。
適切な在庫管理や仕入量の判断は簡単な事ではありませんが、過去の販売に関するデータなどを分析することや、在庫が増えた段階でセールを行うなどして適切な在庫量になるよう早めにコントロールすることで、過剰在庫や需要に対してバランスの崩れた仕入費となってしまうことを回避したり現金化を早め、資金ショートの危険性も低減できるようになります。
支出計画を立てずに運転資金が不足してしまう
今後予想される収入と支出を想定し適切な支出計画を立てることで、運転資金が不足してしまう危険性を大幅に低下させられるようになります。
これは逆に支出計画を立てない会社経営を行っていては、資産を適切に使えず、資金繰りを不安定にしてしまう危険性を増すことになりかねません。
今後の売上げによって得られるであろう利益に対して、材料費や人件費などを含める支出が不足していると判断することができれば、融資などを活用した資金調達により資金を確保したり、支出項目に優先順位を付けることで資金ショートを回避したりしやすくなります。
また支出計画を立てるのは、資金の無駄遣いがないかの確認にも役立ちます。
定期的な見直しなども必要となり手間が発生するのは避けられませんが、資金繰り安定に役立つ期待は高いため、もし支出計画を立てていないという経営者様は、支出計画を立て活用していただくことで、資金繰りの安定が近づきます。
急な出費やトラブルで資金が足りなくなる
地震や台風など、自然災害が少ないとは言えない日本では、災害により建物や設備、商品などが損害を受ける危険は常に付きまといます。
また、たとえ定期的な整備を行っていたとしても、突然のトラブルにより装置が停止した場合には、予想外の大きな修理費が発生する可能性があり、修理が不可能となってしまった場合には設備の更新が急務となってしまいます。
このようなトラブルなどによる急な出費に備えるのは容易ではありませんが、どうにか手元にある資金で対応した結果として、資金ショートの危険が高まってしまうのは、ある意味で致し方ないとも言えます。
しかし設備の修理費など突然のトラブルで発生した費用も、基本的には後払いによる支払いとなるはずであり、支払日までにいかに資金を調達するかが、実際に資金をショートさせてしまうかの大きな分かれ道となります。
可能な限り手元に資金を確保しておくことと併せて、早急な資金調達に対応可能な選択肢を模索しておくことも、トラブル発生時に備えるためには効果的であると言えます。
資金ショートした場合は支払い調整と現金確保が最優先
資金ショートを回避するために対策をできる限り行うことは大切ですが、予測できないトラブルにより資金が不足する危険を完全にゼロにするのは難しく、資金ショートに陥った際にどのように対処を行うか前もって把握しておくことも大切です。
手元の資金が支払額に対して不足している状況とは、取引先との関係を悪化させかねず、最悪の場合には倒産ということになりかねない危機的な状況です。
時間をかけて対応している余裕はあまりないはずであり、優先すべきことやできることから素早く対応していただくことが求められます。
必要なのは限りある資金をどのように活用すべきかを判断する「支払い調整」と、少しでも多くの支払いを終わらせるための「現金確保」となりますが、これからご紹介する8つの選択肢を素早く行っていただくことで、資金ショートのピンチを乗り切れる可能性は高くなります。
それぞれ順に解説します。
現在の資金状況と入出金予定を確認する
資金ショートとなった場合にまず行っていただくべきなのは、「入出金に関して、現状とこれからの把握」です。
その時点でどれくらいの資金を確保できているのかを把握していただき、取引先からの売掛金の回収がいつどれくらい行える予定なのかや、公共料金なども含めた支払予定を確認していただくことが大切です。
いつまでにどれくらいの額が必要であり、タイミングごとに不足しそうな額も確認していただくことで、いつまでにいくらの資金調達を行うべきかや、資金調達を実行すべきタイミングが見えてくるはずです。
売掛先からの入金が遅れるなどして手元資金に不安が生じてしまった場合には、少しでも早く行動を起こしていただくことも大切ですが、慌てて動くのではなく一旦落ち着いて入出金に関しての現状とこれからの予定を立てていただくことで、無駄のない資金調達と支払いを進められるようになります。
初動を間違えてしまうと被害を拡大しかねないため、「現在の資金状況と入出金予定を確認する」ことは非常に重要なポイントとなります。
支払いを延期して資金流出を一時的に抑える
取引先との関係性が重要にはなりますが、支払日の延期や分割しての支払いが可能となれば、資金繰りの負担を軽減することができます。
ただし売掛先にとっては回収サイトが伸びるなどして資金調達スケジュールが狂う原因となるため、無理な交渉をした場合には企業間の関係性に溝を作ることになりかねませんので注意が必要です。
資金ショートの危機を乗り切るのは何より重要ですが、取引先を失うようなことになってはその後の経営を難しくしかねず、支払延期などの交渉を行う場合には、交渉相手と内容を慎重に判断していただかなくてはなりません。
また支払いに関しての優先順位を付けていただく際には、不渡りを繰り返した場合に金融機関との取引が停止されかねない、約束手形や小切手を使用した取引は優先順位を高めにしていただくことを推奨いたします。
融資は個人事業主・中小企業問わず多くの企業にとって重要な資金調達先の選択肢となり、今後の会社運営を念頭において支払先の選択や順位付けを行っていただくことも大切です。
請求書カード払いを使って支払い期限を延ばす
「請求書カード払い」とは、取引先への支払いなどBtoB取引の決済を手持ちのクレジットカードによって行えるサービスであり、このサービスを活用することで手元に現金がない状態であっても取引先への支払いを行うことが可能となります。
また請求書カード払いには以下のようなメリット・デメリットがあります。
| 請求書カード払いのメリット | 請求書カード払いのデメリット |
|---|---|
| 支払いを最大で60日程度先延ばしにできる クレジットカードを保有していれば利用可能 複数の支払いを一元管理できる | カードの利用可能額が請求書カード払いの限度額となる 手数料が発生する 給与払いなど一部利用できない状況がある |
カードを利用したタイミングにもよりますが、最大で60日程度支払いを先延ばしにでき、クレジットカードを保有してさえいれば、複雑な審査もなく利用できる場所がほとんどです。
しかしクレジットカードの限度額以上の利用はできないため、請求書カード払いに利用できる額は保有されているカードに大きく左右されます。
また3%~5%が相場となっていますが、利用の際には手数料が発生するという点もご理解していただく必要があります。
ファクタリングサービスを利用して売掛金を早期現金化する
売掛債権をファクタリング会社と呼ばれる債権の買取業者に売却し現金化するのが、「ファクタリング」と呼ばれるサービスです。
融資よりも短時間で審査が終わる期待が高く、即日での債権買取に対応している場所も少なくはないことから、資金ショートに陥った際にも素早く資金調達を行い現金を確保することが可能となります。
| ファクタリングのメリット | ファクタリングのデメリット |
|---|---|
| 最短即日での資金調達が可能 経営状況が審査にあまり影響しない 負債額を増加させない | 売掛債権の額面以上の資金調達はできない 不良債権は原則売却不可能 繰返しの利用には適していない |
ファクタリングを利用していただくには売掛債権が必須となりますが、決済日を過ぎた不良債権は買取対処とならないことがほとんどですので、手元に決済前の売掛債権を保有していない場合には利用は難しくなってしまいます。
ですがファクタリングは売掛先の経営状況を重視する審査基準により、赤字経営や債務超過の企業も問題なく利用できるという特徴があり、資金ショートの危険が高い状況の企業も売却可能な債権さえあれば、高い確率で審査に通過することができます。
また債権の売買であり融資ではないことから、債権売却後に対象債権の売掛先が倒産したとしても買戻しなどが求められないという点も、資金ショート後の資金繰りのリスク軽減に役立ちます。
手形割引やビジネスローンを活用して資金を確保する
現在では売掛債権を活用した取引が企業間では中心になっており、約束手形を利用する機会は減少傾向にありますが、売掛債権を現金化するファクタリングと同様に、約束手形も「手形割引」を活用していただくことで現金化が可能となります。
ただし手形割引はファクタリングとは異なり、振出人(債務者)の信用情報を重視した審査が行われ、また現金化後にも約束手形に関しての責任を持つ必要(弁済義務)がある点には注意が必要です。
他にも資金ショート時の急ぎの資金調達には、「ビジネスローン」も活用していただけます。
原則的に無担保・無保証人で利用できるだけでなく、通常の融資と比較すれば審査通過しやすいのも特徴となりますが、何より即日資金調達に対応可能な商品が少なくないため急ぎの状況でも利用しやすく頼りになります。
しかしビジネスローンは金利が高くなりやすく限度額は低めになりやすいというデメリットがあり、さらに利用目的に対して十分な借入が行えるかは審査を受けてみなくてはわからないという点にもご注意ください。
新たな融資を受けて資金繰りを安定させる
事業者の資金調達方法としてもっとも一般的である「融資」は、資金ショートのピンチでも利用可能な選択肢となります。
ただし申込先によるものの金融機関から融資を受けるには通常2週間~1ヵ月程度の期間が必要となり、中小企業や個人事業主も利用しやすいと言われる日本政策金融公庫はさらに時間がかかる傾向がありますので、本当に急ぎの状況に利用するには向かないと言わざるを得ません。
資金はショートしたものの取引先から支払い遅らせることを承認していただけた場合など、ある程度時間的に余裕あれば、高額な限度額や低金利も期待できる銀行や日本政策金融公庫からの融資は有効な選択肢となります。
しかし融資を受けるには審査を通過せねばならず、特に経営状況の悪化により資金ショートに陥った企業の場合は、資金ショートに陥った原因とその改善策、さらに金融機関が納得できる無理のない返済計画を提示する必要があるため、丁寧な事前準備を行った上で審査に臨んでいただくことが求められます。
資産を売却して当面の現金を確保する
手持ちの資産を売却し現金化すれば、資金ショートの状況を抜け出すための資金とすることができます。
売却可能な資産としては以下のような物があります。
- 土地、建物などの不動産
- 有価証券
- 遊休設備(社用車や重機なども含む)
- 在庫商品
企業が保有する多くの資産は売却が可能ですが、物によって売却までに必要とする期間が大きく異なり、また売却先によって買取額に大きな差が出ることがありますので、調査や比較をせずに急いで売却してしまうのはあまりおすすめできません。
ですが資産の売却は現金確保に役立つだけではなく、維持費や税金などのコスト削減効果も期待でき、その結果として自己資本比率や総資本経常利益率など企業評価に関する数値が改善することも期待できます。
特に不動産関係の資産については、売却後の資産をリースという形で利用する「リースバック」という方法も徐々に広がっており、資産を活用した資金調達をご検討であれば、こちらの活用も併せてご検討ください。
また資産には売却以外にも担保としての活用方法もありますので、状況によっては動産・債券担保融資(ABL)なども資金調達の選択肢となります。
専門家に相談して再建までの流れを整える
資金ショートに陥ってしまった際には「顧問税理士・行政書士・中小企業診断士」などの専門家に相談していただくのもおすすめです。
また公的機関としては、「日本政策金融公庫・中小企業基盤整備機構・中小企業支援センター」などが相談先の候補となります。
専門家に相談していただくことで、資金繰りに関する改善点や経営においての問題点についてのアドバイスを受けることが可能となり、公的機関など相談先によっては各種の融資制度の紹介を受け、資金調達に活用できる可能性もあります。
このように各専門家への相談を行うことで、資金ショートに陥ってから再建への流れを明確にしやすくなり、専門的知識とアドバイスによって最短の道を歩みやすくなります。
資金ショート後の相談も有効ではあるものの、資金繰りに不安を感じた段階や、特に経営に問題がない状況でも定期的に専門家に相談していただくことで、資金ショートに陥る危険を未然に解消しやすくなります。
資金ショートを防ぐには日々の資金管理と予測が重要
資金ショートに陥ってから素早く適切な対応を行っていただくのは、自社の倒産や取引先への迷惑を避けるために非常に重要となりますが、本当に大切なのは「資金ショートに陥らない会社経営」を目指すということです。
これまでにご紹介した資金ショート時の資金繰り改善方法などによって、資金ショート後の資金繰りのピンチを乗り切るのも可能となりますが、支払いを遅らせたことで売掛先から失った信用を取り戻したり、悪化した経営状況を安定させたりするには、多くの時間と労力が必要となります。
しかし日々の資金管理と売上げや在庫管理などに関する予測がしっかりとできれていれば、資金ショートを未然に防ぎ、会社の売上向上や事業拡大に向けて進みやすくなります。
現在、経営状況が安定しているという経営者様も、これからご紹介する中に不足している対応あれば、この機会に始めていただくことを推奨いたします。
それぞれ順に解説します。
資金繰り表を作成して支払い時期を可視化する
一定の期間内における現金収支を表としてまとめた「資金繰り表」は、過去のお金の動きを確認するためだけでなく、資金ショートに陥る危険を予測し対処するのにも大きく役立ちます。
- 実績資金繰り表—過去の入出金実績を記載した資金繰り表
- 予定資金繰り表—今後予測される入出金を記載した資金繰り表
資金繰り表には上記の2種類がありますが、これらを活用していただくことで、これからご紹介するようなメリットが得られます。
- 現在の資金繰りにおける問題点や改善点を見つけられる
- 金融機関からの信頼を受けやすくなる
- 今後の収支を予測するのに役立つ
資金繰り表を作成していただくことで得られる主なメリットは、上記の3点となります。
特に3つ目の収支予測に関するメリットによって、資金が不足しそうなタイミングに間に合うように融資などを活用した資金調達が行えるようになるため、資金ショートの危機を回避するのに大きく役立ちます。
また資金繰りの問題点改善や融資を受けやすくなるというメリットも、結果的に資金ショートの危険を未然に回避したり、現金が不足した際にもスムーズに対応できたりするなど、資金繰りを安定させる効果は小さくありません。
資金繰り表はEXCELなどで作成可能ですが、様々なサイトでテンプレートが無料配布されていますので、そちらを利用していただくのもおすすめです。
毎月のキャッシュフローを確認して早めに対応する
キャッシュフローとは、その名の通り会社経営における現金(キャッシュ)の流れ(フロー)を指します。
あくまでキャッシュフローは現金を対象とするため売掛金や買掛金は含まれず、「営業活動・投資活動・財務活動」の3つに分けて分析を行うことで、利益だけに注目せずに、損益計算書などでは見えにくい経営の健全性を判断することができます。
キャッシュフローを正しく把握することができれば、利益が出ていても資金がショートし経営不能に陥る「黒字倒産」の回避も難しくはなくなります。
キャッシュフロー計算書は、損益計算書や賃借対照表と併せて「財務三表」と呼ばれており、上場企業にはキャッシュフロー計画書の作成が義務付けられていますが、上場企業以外も作成しておいて無駄にはなりません。
ただし確認の頻度が少なくては手遅れになることも考えられますので、現金の流れの問題を素早く見抜き対応するためにも、できる限り毎月、キャッシュフローの確認は行うようにしてください。
固定費や在庫を見直してお金の余裕をつくる
固定費の削減や在庫の見直しを行うことで、手元にある資金に余裕が生まれ、資金がショートする危険性を低下させることができます。
「人件費・家賃・減価償却費・通信費・光熱費・広告宣伝費・リース料」などが固定費に含まれますが、毎月発生する費用であることから、長いスパンで見ると削減効果も大きくなります。
ただし人件費を削減した結果、従業員のモチベーションを低下させてしまっては、会社経営において逆効果となる可能性もあるなど、短絡的に削減を行わず、生産性を維持しながら無駄を省いていくことが大切です。
また多過ぎる在庫は、倉庫など保管スペースを維持するための費用を増加させ、キャッシュフローを悪化させてしまう原因ともなります。
過去の販売実績などから在庫は適量を判断していただくことが重要ですが、在庫が増えすぎた場合には商品の劣化や流行の時期を逃す前に、割引セールなどを行い販売促進に努めていただくのも効果的です。
また在庫管理システムを導入していただくことで効率的な在庫管理が行いやすくなり、さらに管理に必要だった人件費の削減効果も期待できるようになります。
複数の資金調達手段を準備してリスクを分散する
資金調達のために融資を活用されている企業は少なくありませんが、追加の融資を断られてしまった際に代替えの資金調達方法が見つからない場合には、資金ショートの危険が大きく高まることになりかねません。
融資以外にも「ファクタリング・補助金や助成金・投資家からの出資・クラウドファンディング」など、資金調達の選択肢は様々あり、複数の選択肢を使えるよう準備しておくことができれば、何らかの理由で資金調達が上手くいかなかった時にも慌てずに対応していただけるようになります。
また融資に頼り過ぎた結果、負債額が増加し過ぎて債務超過に陥るなど、1つの資金調達方法に頼り過ぎたことがデメリットに繋がることもあり得ますが、負債を増やさずに資金調達が行えるファクタリングも併用するなど、複数の資金調達方法を活用していただくことで、デメリットが解消できることも少なくはありません。
だだし融資実績が増えれば融資額の増額や金利引き下げが期待できるようになるなど、使い続けることで得られるメリットもありますので、メインとなる資金調達方法を決めておいていただくことも大切です。
銀行や取引先と信頼関係を築いて安定化を図る
融資を受けている企業が資金をショートさせてしまいそうになった場合には、返済日までに金融機関に対してリスケジュールを希望し、返済額を減額させることで資金ショートを回避できる可能性が向上します。
買掛金の支払いが難しい状況でも、取引先へ相談し決済日を先延ばしにしてもらうことができれば、同様に資金が不足する危険を回避できる期待が高まります。
また売掛債権の決済日を前倒しにしてもらうことで、支払いに必要な資金を確保可能となります。
ですが金融機関でのリスケジュールも、取引先への支払延期や売掛金の回収の前倒しも、どの場合でも高い信頼関係がなければ実現は期待できません。
金融機関にとっては支払期間が延びることがデメリットになる可能性があり、取引先は債権回収が遅れることで資金繰りに影響が出る危険があるため、交渉は容易にはまとまらないことが予想されます。
しかしトラブルを起こさずに取引実績を重ねることができていれれば、交渉が上手くいく確率は高くなるはずであり、金融機関や取引先と誠実な付き合いを続けて信頼関係を築き上げていくことが、最終的には自社を助ける事になるかもしれません。
資金ショートを回避した企業の成功事例と学び
決して「資金ショート=倒産」ではなく、資金が不足した状況からでも、経営者様の判断と努力により経営を立ち直らせた企業はいくつも存在しています。
ですがやはり重要なのは資金ショートの危機を回避することであり、「資金ショートの危機を回避した企業の成功事例」には多くの学びがあります。
安定した経営を続けていても黒字倒産の危険はゼロではなく、思わぬところに資金ショートに陥るきっかけが隠れているかもしれません。
逆に資金が不足する未来が目の前に見えていたとしても、適切な判断により資金調達に成功できれば、支払いが不可能となり取引先に負担をかけることもなくなるはずです。
これからご紹介する成功例を参考にしていただき、会社経営における1つのヒントとしていただければ幸いです。
資金繰り表を導入して早期発見に成功した例
- 家族経営の飲食店
- 利益の低下による資金繰りの不安から資金繰り表を導入
代々家族経営を続け安定した売上を残してこれてはいたが、近隣店舗の影響や材料費・燃料費の高騰により利益が低下しており、資金がショートする不安が増大した。
また資金繰りに関しても経験に頼っている面が大きかったため、利益の低下に対応するための現状把握と今後の予測への活用を目的として資金繰り表を導入。
過去数ヶ月分の収支情報から売上の変動や固定費の増加など、資金繰りへの影響が小さくないデータが目に見えるようになったことで、売上の予測が立てられるようになったり経費の見直しが行えるようなり、資金の管理が容易となった。
- 資金繰り表によって今後の収支の予測が可能となり資金繰り計画が立てやすくなる
- 黒字倒産のリスク軽減効果が得られる
支払い条件を交渉して資金を安定させた事例
- 部品製造業
- 回収サイトの長期化が資金繰りを圧迫
大手企業とも取引があり比較的売上そのものは安定しているものの、回収サイトが長く支払いサイトが短めという状況であったため資金繰りが難しく、資金が不足しそうな時期にはファクタリングやビジネスローンなどを活用して資金調達を行っていた。
しかし根本的な解決にはならず、ファクタリング手数料や利息の支払いが資金繰りの負担になることから取引先との交渉を選択。
資金繰りの難しさをキャッシュフロー表などを用いて説明し、回収サイトの短縮に成功。
また買掛金に関しても交渉を行い複数の取引先から理解を得られたことで、資金繰りは大きく改善した。
- 取引先との関係性が重要であり、関係性への悪影響がないかを考慮しながら交渉先を選ぶことが重要
- 感情論などに頼るのではなく、キャッシュフロー表など資料を用意して現状を誠実に伝えることが大切
専門家と連携して経営を立て直した企業の話
- 食品加工工場
- 融資の審査に通過できず資金繰りが困難に
資金がショートをしてしまうのを回避するために金融機関へ融資を申込んだが審査通過できず、資金調達のリミットが近づいてきた危機感から専門家(経営コンサルタント)へサポートを依頼。
資金が不足しがちな原因となっていた、原材料費や人件費の高騰に関しての対策と併せて、専門知識を活かした債務状況の分析や適切な返済計画の立案などのサポートを受けられたことで、無事に金融機関の審査に通過し資金調達に成功することができた。
資金調達後も無理のない返済ができており、コスト削減も行えたことで経営状況は大きく安定した。
- 具体的で信ぴょう性の高い経営の改善案や返済計画の提案が受けられる
- 専門家の客観的なサポートを受けているという事実により、金融機関からの信用を得やすくなる
在庫と経費を見直して利益を増やした成功例
- 電線(ケーブル)製造会社
- 多種多様な電線やコネクタなどのパーツの保管に場所と人件費を消費
設備メーカーなどからの依頼に迅速に応えるため、多種多様な電線やコネクタを保管していたが、在庫管理に多くの時間が割かれることになり人件費が増加してしまい、資金繰りの負担になっていた。
在庫管理システムを導入した結果、過剰在庫やコネクタなどの欠品がなくなり、在庫管理の手間を大きく削減することができた。
また手作業に頼っていた部分が激減し、作業者のミスによる経費の無駄も削減され作業効率自体も改善したため、利益向上にも繋がった。
- 在庫管理を適切に行うことで過剰な在庫を持たずに済み、人件費を含めた経費削減の効果が得られる
- システム化によって手間や人為的ミスが減少し、作業の効率化が期待できるようになる
資金ショートに関するよくある質問
倒産の危険も高まる資金ショートは、経営者様にとって絶対に避けたい、会社経営における大きな問題の1つです。
この記事の最後に、そんな資金ショートに関するよくある質問を4つ、ご紹介させていただきます。
普段から自社の資金の流れや収支実績を正しく把握していただき、資金繰りを柔軟に行えるように備えていただくことで資金ショートに陥る危険は低くなります。
ですが、もし経営状況の悪化や売掛先の倒産などの思わぬトラブルで資金が不足しそうになった場合や、実際に不足してしまった時にも、諦めず最善の選択肢を探していただくことで、大切な会社を守れる可能性は大きくなるはずです。
資金ショートからの復活って可能なの?
資金ショートが会社経営において危機的な状況であることは確かですが、資金ショートからの復活は不可能なことではありません。
しかし資金ショートから復活するためには、適切な対応を素早く行っていただくことが必須です。
まず行っていただくべきは「現状把握」であり、希望的観測をせず悲観的になるのでもなく、資金繰り表などを参考に客観的に現状を把握していただくことが大切です。
続いて支払いに関しての優先順位を決めていただき、売掛金の早期回収や買掛金の支払い延期の相談、ファクタリングによる現金調達など、短期間で資金繰りの改善が期待できる選択肢を活用し対応していただくことで、資金ショートの危機を乗り切れる可能性が高くなります。
ですが資金ショートから本当の意味で復活するためには、会社経営の問題点を見つけ出す必要があります。
支払いを一段落させた後は、売上げの向上を目指すだけでなく、資金調達の選択肢を増やしたりコスト削減を行ったりするなど、資金繰りを安定させ企業としての成長軌道に乗せるための判断と行動を迅速に行っていただくことで、資金ショートからの復活が近づきます。
資金繰り表はどのくらいの頻度で更新すればいい?
資金繰りに特に問題が発生しておらず経営状況が安定しているのであれば、更新にかかる手間を小さくする意味でも、毎月月末に更新していただくことをおすすめします。
たとえ資金繰りに問題を全く感じていないとしても、更新頻度は月1回以上を目指してください。
ただし資金繰りが難しくなっている状況では毎週以上のペースで更新を行っていただくべきであり、資金繰りが特に厳しいと感じられる場合には毎日更新していただき、随時状況確認と今後の予測を立てていただく必要があります。
また資金繰り表はただ更新するだけでは会社経営において効果を発揮しているとは言えません。
売上げに対しての仕入費や様々な費用とのバランスを確認し融資などの資金調達を行うかを検討していただいたり、取引先に対して売掛金・買掛金に関する取引条件の見直し交渉を希望するかどうかなど、経営に関しての判断材料として活用していただいてこそ、資金繰り表はその価値を発揮することができます。
金融機関に相談するときの注意点はある?
資金ショートの危険を回避するためにリスケジュールや追加融資について金融機関に相談する際には、資金繰り表などを用意し現状の収支に関する可能な限り詳細なデータを提示していただくことが大切です。
また資金がショートしてしまった主な原因を根拠を示しながら説明できるようにしておくことで、適切なアドバイスを短時間で受けられる期待が高くなります。
逆に金融機関からの信頼を失うのではと、事実ではない説明をしてしまうのは逆効果になる危険の方が大きく、事実を包み隠さず正直に伝えていただかなくては信頼は得られません。
手元の資金がショートしそうと感じた場合や不足してしまった後でも、状況が悪化するのを避けるためには少しでも早く金融機関に相談されることをおすすめいたします。
金融機関にとっても資金ショートによる貸倒れを避けるという目的がありますので、親密な対応を受けることができるはずです。
信用を回復するためにできる取り組みは?
買掛金の支払いができず資金ショートによる被害を取引先に与えてしまった場合などでは、積み重ねてきた信用を大きく損ねることになりかねません。
失った信用を取り戻すのは容易ではありませんが、可能な限り早期に誠実に状況の説明と謝罪を行うべきです。
また今後の資金繰り改善や売上向上など、資金ショートに至った問題解決に向けての具体案を提示していただくことも信用回復のためには大切ですが、情報の信ぴょう性が低くてはさらに信用を失いかねませんのでご注意ください。
最終的には取引を続ける中でトラブルを起こすことなく、地道に実績を積み重ね直すことでしか失った信用を取り戻すことはできませんが、取引先に不安を感じさせないためにも密にコミュニケーションを取っていただくことも重要です。
迷惑をかけてしまったからと取引条件を譲歩し過ぎるのは、自社の経営状況をさらに悪化させることになりかねませんので、交渉を行う際にはどこまで譲歩できるかなどを事前検討しておくことが必要となります。